「朋有り遠方より来たる、亦楽しからずや」なんて言葉をふと思い出した。これ習ったの、中学だったか高校だったかもう忘れたけど、論語の一番最初の方に出てくるので、論語の中でこれだけ覚えてる。現代社会で、ひょっこり友人が訪ねてくるなんてことはもうないだろうから、これに当てはまるようなこともないなあと考えていて、ポール・マッカートニーとジョン・レノンの会話で、どっちかが相手にそんなこと言った話を思い出した。
たぶんビートルズが解散した後のことで、ポールがジョンの家を不意に訪れたか、その反対だったかで、訪れられた方が、「もう僕たちはそんな歳じゃないんだ、リバプールの頃とは違うんだよ」みたいなことを言ったとかいう話。来るなら予め連絡しとけよってことなんだけど、「もう孔子の時代とは違うんだ」と言えば面白かったのにと思う。孔子なんて知らんかな。
* * *
それに似たことだけど、退職してから慣れなかったことが一つある。電話だ。電話はかつてはそういう予めの連絡に使われる手段だったと思うけど、僕の職域ではその電話をすることも予め連絡するというのが習慣になっていた。テキスト・メッセージとか、Messenger とか、WhatsAppとか、Signal とか相手によって使い分けるけど、「今話せるか?」とか「話したいことあるけど、何時頃話せる?」みたいなメッセージを送るのが第一ステップで、それで日時を決めてから実際に電話なり、Zoomなり、Skypeなりで話す。
長い間そういう文化にいたので、いきなり電話して話させるというのは、とても強引というか、横柄に感じる。日本社会では、いきなり電話していいんだ(そうでもない人もいると思うが)と言い聞かせるが、今でも、電話は暴力的な気がする。電話をかける方が、電話をかけられる方の時間を当然のように支配していいわけがないと思ってしまうのだ。
僕の職域界隈では、誰もこれを確立した習慣だとか、ましてやエチケットなどと意識していなかったけど、自然にそれが(それというのは、いきなり電話するのではなく、お伺いメッセージを入れるという慣行のことだけど)、定着していったのは、電話をかける相手の時間のことを考えるからだろうと思う。
その相手は、今誰かと楽しく話してる最中かもしれないし、会議中かもしれないし、誰かと大喧嘩をしているところかもしれないし、何かを真剣に考えてる途中かもしれないし、食事中かもしれないし、排便中かもしれない。だから、色々な可能性を考えると、とてもいきなり電話など出来るものではない。単に相手の生活をちょっと尊重する気持ちがあれば自然発生する慣わしだと思うが、そんな話を日本ですると、これをエチケットだとか、マナーだとか言い出す手合いが出てきて、カタチだけそろえるいつものアレになってしまうので、言わない方がいいかもしれない。
* * *
話が逸れた。友人がひょっこり現れるなんてことは現代社会ではまずないことだ。しかし、そしたら、なぜこんな論語の一節を思い出したかというと、今でも、長い間会ってない友人がひょっこりとMessenger や、WhatsAppや、Signal で現れることがあるからだ。「お、朋有り遠方より来たるだ」と一人で思っている。
遠方より電子的に来たる朋に大した要件があるわけではない。直近から遡っていけば、オランダ政府の友人がプロジェクト立ち上げの相談をしてきた。その前は、チュニジアの友人が国連の次のポストへの推薦状を書いて欲しいって話(国連の採用は、筆記と面接を通過すると必ずReference Check をするので、そのこと)、その前はアトランタでブロックチェーン関係のスタートアップを3年くらい前に立ち上げた友人が今、人を募集しているが誰かいい人いないかって話(うまく行ってるんだろう。良かった、良かった)、その前はジュネーブの友人がガザ関係の記事を書いたからそれを広めてくれという話、その前はオタワの友人がガザ関係のビデオを送ってきて拡散してくれという話(もう拡散されていた)、その前はベルリンの友人が家族旅行中だがナワリヌイ氏の死に腹が立ってるというお話。思い出してみると、どんどん続いていく。話し始めると、「それ、5年前に言ったよね」「あーそうだった」みたいな話が色々と出てきて「亦楽しからずや」という気分にもなる。
* * *
しかし、人生が良い思い出だけで埋まってるわけがないので、”思い出す”ということが痛みをぶり返すこともある。
6、7年前だと思うが、ある日、フィールドにいるスタッフが死んだという知らせを受けた。その頃までには、恐ろしいことに、スタッフが死ぬということは、僕の中では珍しいことではなくなっていた。また銃撃戦に巻き込まれたとか、爆弾が飛んできたとか、直ぐに頭に浮かんだのはそんなことだった。どこのスタッフなのか訊くと、カブールという返答。おかしい。その頃、カブールで戦闘は起きていない。どこかで地雷でも踏んだのか?
直ぐにNY事務所でアフガニスタンを担当しているチームとミーティングをして事情を確かめた。
「病気で死んだんです。」と担当チームのリーダーが言う。
「病気?なんの?」と聞き返した。
「癌だったらしいです」
「癌だった?それで仕事してたの?」
「ええ…」
「赴任前にメディカル・チェックしなかったのか?」
「したはずなんですが…」
そんな会話を続けてようやく事情が見えてきた。そのスタッフは、コソボから来ている地雷処理をしている、いわゆるDeminer だった。自分が癌であることをもちろん知っていたし、治療を受けるために休暇を取ってコソボに帰ったことが何度かあったらしい。しかし、必ず戻ってきて、また仕事を続けていた。コソボには、妻と娘が2人、息子が2人いた。一番大きい長女が高校生なので、みんなまだ小さい。彼は家族を養うためになんとか仕事を続けようとしていたのだった。だから、自分の病気のことは極力大っぴらにならないように、大したことないという話っぷりだったそうだ。
赴任地に行く前にメディカル・チェックや、セキュリティの訓練を受けることは義務になっているのだが、メディカルでは止められなかったようだ。しかし、同じ事務所の同僚たちは?そこの所長は?NY事務所の担当チームは?誰も何も知らなかったというのか?
そして、僕は何も知らなかった。どこにぶつければいいのか分からない怒りが湧いてきた。末期癌の人間を働かせていたということなのか。その頃、僕は全部で23カ国で展開している平和維持軍やその他の平和活動の中で地雷対策、IED対策、テロ対策などをNYで統括する立場にいた。フィールドにいるそれぞれの所長が僕の直接の部下で、その下にヒエラルキーがあり、さらにその下に国連が資金を提供して、実際に業務を遂行する民間企業やNGOなどがいた。全部合わせると2万4千人の大所帯だった。2ヶ月に一回フィールドに行ったところで、全員に会えるわけでもないし、みんなの顔や名前を覚えれるわけでもない。
NY事務所では、国別担当チームを6つ作り、それぞれのチームが数カ国を担当していたが、そのチームでもフィールドでの日常を全て把握するのは不可能だった。非難しているわけではない。NYの担当チームはみな限界まで働いていた。もっと予算があれば、もっと人が雇えるのだが、地味な仕事に予算は回ってこない。
アフガニスタン担当チームのリーダーが、また一つ嫌な知らせを持ってきた。
「彼は保険に入ってませんでした」と言う。
「は?なんにも?そんなことどうして起きるんだ?」
亡くなったコソボのDeminer は、国連職員だが、フルタイムの職員ではなかった。日本で言う非正規職員のような期間限定の契約で給料は多めだが、それで医療保険やその他保険を自分で払うという形になっていた。だから、手取りは1.5倍くらいに設定されている。医療保険加入の証明は提出が義務化されているが、生命保険の提出は任意になっていた。おそらく節約のために入らなかったのだろうと推測するが、実際のところは分からない。僕が初めて国連の仕事を始めた時、指1本なくなったら◯◯ドル、足一本なくなったら◯◯ドルなどと列挙した保険の説明書をもらったので、うぉっと思ったのを覚えているが、そういう強制的な保険がなかったのだろう。
「で、何かないのか?」
「国連事務次長に感謝状を書いてもらうのはどうでしょうか?」と担当チームのリーダーは言う。
「それはやろう。後で話してみる。でも、紙だけか?」
「盾とかですか?」
「いや、そういう意味じゃなくて、子ども4人いるんだろ?お金はないのか?」
癌を患いながら、家族のもとを離れて、あれだけ危険な仕事をして、死んだら紙一枚か。これはやりきれないと思いながら、話を聞いていた。
「◯月◯日に亡くなったので、その日までの日割り計算をして今月分の給料を払いますが」
「え?今月の給料も全額払わないのか?そんなバカな。」
「ええ、契約上はそうなっていますので…」
「なんとかしようよ。なんとか」
経理に電話して、なんとかならないかと訊くと、契約がそうなってるんなら仕方ないという返事。でも、そのプロジェクトのドナーが払っていいというなら、払えると言う。
「おー、そうか、ありがとう!」と言って電話を切った。速攻でドナーの担当者に事情を説明した。そのプロジェクトはあと3ヶ月くらいで終了する予定で、彼の契約もその期間に合わせたものだった。僕はドナーの担当者に「プロジェクト終了日までの全額給料を払えないだろうか。もし払えないなら、余ったお金はドナーに返すことになります」と言った。出したお金が戻ってくるというのは、ドナーにとって嫌なことランキングで上位にある。ドナーにとっては、お金を出すということ自体が一つの業績になっているからだ。その業績に誰もケチをつけられたくない。
そのドナーは納得してくれた。よし全部払える。少ないけど、紙一枚だけよりマシだ。同時にスタッフに募金を頼んだ。こういう仕事をしている人たちの同志感は強いし、大変な事情も理解してくれる。それで少し足しになった。結局全部で1千万円くらいにしかならなかったけど、ないよりマシだ。
お葬式の日程の連絡が来た。僕はこのお葬式に行くことを考えていたが、ちょうどコペンハーゲンとロンドンへの出張の日程に重なっていた。国連事務次長の感謝状をメールで送るのは初めてではなかったけど、なんかなあと思っていた。紙一枚とは言え、手渡しするべきじゃないだろうか。結局、コペンハーゲンへの到着を1日遅らせることにして、コソボに行くことにした。
コソボには自分が担当している事務所がなかったので、国連の兄弟事務所に事情を話して、便宜供与のお願いをした。空港に着くと、ホテルと車が用意されていた。とりあえず、その事務所に行くと、全体に静かなのに直ぐに気がついた。彼らはみんな亡くなったDeminer の友達だったのだ。それはそうだろう。数少ない同胞の国連職員として、お互いに知り合いだったのは不思議ではなかった。
そこで色々と彼の生前の話を聞いた。彼は時々休暇をとってコソボに戻っていたが、コソボの医療よりレベルの高いトルコのイスタンブールまで治療を受けに行っていたということを知った。彼はなんとか生きようとしていた。その事務所の人たちはそれをみんな知っていた。
翌朝早く、コソボの事務所が車と運転手を提供してくれて、お葬式のある彼の村に向けて出発した。すごい山奥に入っていく。途中の景色がきれいで見惚れた。3時間かかってやっと着いた。
山肌に広がる広大な墓地に村の人たちが数百人集まっていた。みんなが墓地の中を静かに歩きながら、ボソボソと話をしている。外国人は一人だけだったように思われる。というか、たった一人スーツを着た東洋人というのはまったく場違いだったろうと思う。

最後に彼の家に行って残された家族に会った。子どもたち4人は特にしおれた様子もなかったが、お母さん、つまり彼の奥さんの明らかに疲れた顔には不安そうな表情が漂っていた。一番下の小学生の男の子はお母さんにしがみついて隠れるようにして謎の東洋人を見ている。高校生の長女だけが少し英語が分かるので、ポツポツと応答をしてくれた。あとは、コソボの事務所から来てくれたスタッフが通訳してくれた。何か親戚とか知り合いの集まりがあるようで、忙しそうなので、お母さんにはできるだけ早く残りの給料と同僚たちのカンパを振り込むと伝えて、子どもたちにも何かあれば連絡しておいでと言って、名刺をあげてお暇した。
それから、また忙殺される毎日が続き、コソボのお葬式のこともすっかり忘れて1年くらい経ったある日、めったに見ることのないFacebookにメッセージが届いていた。ほとんど全部無視するが、見慣れない名前が気になって、開けてみたが、その名前が思い出せない。しばらく見ていて、あっ!と思った。
それは、コソボのお葬式で会った一番下の男の子からだった。名刺の名前をFacebookで検索して僕を見つけたんだろう。僕を覚えていたのか。英語を勉強しようとしてるのだろうか。コソボで元気に生きてるのだなと、お父さんを失った子のことを考え始めると、涙が出てきた。気がついたら、もう何十年も経験していない嗚咽になっていた。本当に悪いことをした。
これも、朋有り遠方より来たるだった。
END
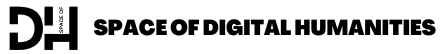

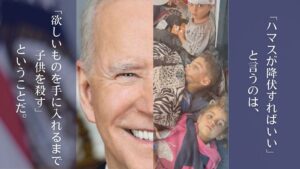









Comments
List of comments (2)
貴重なお話をありがとうございます。
ありがとうございます。