何かとても重大で深刻な知らせを聞いた時、即座に強い大きな感情が湧いてこない。映画の中のような劇的なシーンとはかけ離れたほぼ無反応な自分がいる。
約10年前父が亡くなった時も、約1年前母が亡くなった時も、そうだった。認識はしている、でも情緒が反応しない、とでもいうか。身体も心も活動が止まっている。
音が無い空間に一人でいるような感覚。耳が聞こえなくなったわけではない。ありとあらゆる生活音に満ちていることは認識している。それが耳に入って来ない。
周りを見渡しても、まったく普通の風景のはずだが、目に入るものを頭が素通りしている。自分だけその場所にいないように感じる。
そして、何かの拍子に発作のような嗚咽が始まる。
* * *
小さい頃、僕が、いや家族全員がお姉ちゃんと呼んでいる人がいた。同じ家に住んでいたのか、近所に住んでいたのか覚えていない。そのお姉ちゃんは、実際は僕の母の妹で叔母であったが、叔母なんて概念を理解する前だから、お姉ちゃんと呼ぶことになったのだと思う。
僕が幼稚園児の頃、お姉ちゃんは二十歳くらいだっと思う。小学校の低学年の頃、お姉ちゃんは結婚した。結婚式というものに初めて行ったのがその時だった。式は近所のホテルであったが、ホテルという建物に入ったのもその時が初めてだった。三々九度という儀式を知ったのもその時だった。何が面白いのか分からないが、それ以後お正月になると、三々九度ごっこをするようになった。
幼稚園に入る前か入ったばかりの頃、一歳下の妹と僕と近所のじゅんこちゃんの3人で遊んでいた、ある日のことをよく覚えている。今から思うと不思議に思えるかもしれないが、その頃、昭和30〜40年代の日本では、そんな歳の子どもが保護者なしで、自由にブラブラと遊んでいた。
そのある日、僕たち3人は近所のどこかの会社の寮か何かのテニスコートを囲む金網の外の芝生の上で遊んでいた。その芝生の金網と反対側は崖になっていた。もの凄く高く見えたけど、おそらく数メートルだったのではないか。
僕はその崖に腰掛けた。そこも芝生の続きで草で覆われていた。スルッと滑って落ちるような感覚があったのを覚えてる。妹もそこに腰掛けたいと言って、僕はそれを止めたのも覚えている。その後、どうなったのかはっきりしないが、妹は崖から落ちた。
僕とじゅんこちゃんは、大きく迂回して崖の下に走っていった。周りには誰もいなかった。妹はそこに横たわっている。大人を探さないといけないと思った。が、僕とじゅんこちゃんが二人とも探しに行くと、妹が一人になる。僕はじゅんこちゃんに、おかあちゃん呼んできてと頼んだ。僕はそこに妹と二人で残った。
その後、結構大きくなるまで、親戚が集まったりすると、僕の手柄話のようにこの顛末が語られた。褒めているつもりだというのは分かったが、ちっとも嬉しくなかった。”妹が落ちてもうた”という衝撃の方がはるかに大きく残っていたからだと思う。
じゅんこちゃんをおかあちゃんを呼びにやった後のことは、何も覚えてない。おかあちゃんが来たのか、救急車が来たのか、まったく何も。
妹の頭は割れていて、その街で一番大きな病院に入院した。大人がシミン病院と呼ぶので、自分もそう言っていたが、シミン病院が市民病院だとは長いこと知らなかった。
それから、母とバスに乗って市民病院に通う生活が始まった。毎日行っていたのか、数日おきだったのか覚えてない。しかし、母は、今から思えばだが、かなり忙しい日々を送っていたと思う。
ある日、母に保育園というところに連れて行かれた。保育園の意味を知らなかったが、そこに行くと、ちょうどお昼寝の時間でたくさんの子供が寝ていた。そこに置いて行かれるという恐怖でパニックに陥った僕はギャン泣きして、いやや、いややと必死に母に抵抗した。
妹が入院中で、別の小さい子供を一人で家に置いておくのが、いくら当時といえども、母は気がかりだったのだろう。保育園という策に行き着いたのは、今ならよく分かる。しかし、当時の僕にとっては、生きるか死ぬかの分かれ目のようだった。
「かしこーしてなあかんで」と言われて、僕は一人で家にいることになった。今でも一人でいるのが一番楽なのは、ひょっとしてその時の経験のせいなのか、生まれつきの性格のせいなのか分からない。
その頃から、僕は絵を描くのが好きだったらしく、一人でクレヨンで絵を描いてることが多かったらしい。ある日、よく色の出るクレヨンを見つけて、階段の踏み板の端に一段ずつ、おそらくデザインのつもりで何かを描いていった。その色のよく出るやつは、母の口紅だった。母は怒った。
それから、僕は近所に住む鬼ばばあのところへ送られることになった。鬼ばばあは、油屋の屋根裏に住んでいた。その油屋は、江戸時代から続いていると思われる古い建物だった。いったい何を売っていたのか分からないが、薄暗い店の中を通り過ぎると裏庭に出て、そこから屋根裏部屋に上がる階段があった。
屋根裏には、足軽の持つ槍や帽子のようなものや甲冑などが置いてあった。高さの低い座敷机のようなものがいっぱい並んでいて、子どもたちが絵を描いていた。鬼ばばあはそこの監督兼絵の教師だった。

鬼ばばあは恐ろしい顔をしていたが、もの凄く美しい水彩画を描いた。僕がどれくらいの頻度でそこに通っていたのか覚えてないが、毎回いろんな絵の描き方を教えてくれた。絵の具の時もあるし、クレパスやクレヨンの時もある。そこは一人で絵を描いていれば、時々鬼ばばあが手直ししてくれる以外はほったらかしで楽しかった。
母は、口紅をだいなしにした罰のために、僕を鬼ばばあのところに送ったのではなく、僕が絵を描くのが好きそうだと思って、鬼ばばあを見つけてきたのだと僕は思っている。
昭和30〜40年代の日本はまだ貧乏だった。池田首相が所得倍増計画をぶち上げたのが昭和35年(1960年)だから、高度成長と名付けられるような時期が到来する前の話だ。日本人は貧乏から抜けだすために必死に働いた。誰もが忙しかっただろう。
今でいうデイケアのようなものがなかったので、忙しい親たちは子どもの世話は大変だったろうと思う。街の中に子どもたちはぷらぷらしていたし、鬼ばばあのようにそんな子どもたちのためのデイケアの役割を果たす人もいた。
僕に父との会話の記憶がほとんどないのも、昭和30〜40年代の必死に働く日本のサラリーマンだったことが少なからず影響していると思う。記憶がないというより、会話をすることがまれにしかなかったからだ。私鉄の会社で働いていた父は、夜勤があり、早朝出勤があり、とても不規則な生活をしていた。
僕の小さい頃の家族の記憶に、お姉ちゃんが大きく存在しているのは、まだ結婚する前のお姉ちゃんが小さい子ども二人を抱えて奔走する我が家を色々手伝っていたからだろうと推測する。
僕の家族の記憶は、母とお姉ちゃんと妹の女3人のようだった。
頭の割れた妹はその後完治して、何もなかったかのように生活し始めた。
鬼ばばあのところに機嫌よく通う僕は、ある日鬼ばばあが色紙に水彩画を描かせくれ、大喜びでそれを家に持って帰った。お姉ちゃんはそれを僕と同じように気に入ってくれ、僕はその色紙の水彩画をお姉ちゃんにあげた。お姉ちゃんは将来僕が有名な画家になるまで、ずっと持っておくと言ったのを覚えている。
* * *
去年85歳の誕生日の翌日亡くなった母は、お姉ちゃんと二人で生活していた。母の夫(僕の父)は10年前に亡くなり、お姉ちゃんはずっと前に離婚していた。
母は家族から見ると明らかに認知症が始まっていたが、他人と喋る時は急に普通の人になり、なかなか認定されなかった。日増しにお姉ちゃんの負担が大きくなっていった。その結果、お姉ちゃんに僕は自分の親の介護を押し付けてるわけだから、とても申し訳ないことをしていた。
母の入れる介護センターを探していた去年のある日、「頭が痛い」と言って、母は意識がなくなった。その日から3ヶ月間入院して意識が戻ることはなく死んだ。コロナのために3ヶ月間誰も母の姿を見ることは出来なかった。

最期まで母の面倒を見続けてくれたのがお姉ちゃんだった。感謝のしようがない。母が亡くなってから、お姉ちゃんは一人で住むアパートに引っ越した。その直後、癌が見つかった。
入院と退院を繰り返すお姉ちゃんの生活が始まった。いつ電話しても、シャキシャキ喋って元気そうだが、おそらくその喋り方が性格なのだろう。いつも前向きで、暗いところを見たことがない。辛い療法をしていると他の人には聞くが本人はそんなことを言ったことない。離婚後、もらっている年金だけで生活するのは楽なはずはないが、そんな文句も聞いたことがない。
しばらく電話してなかったので、一昨日電話した。2回電話したが出ない。3時間ほどしてから、向こうから電話がかかってきた。そんなことはめったにない。外国への電話のかけ方が分からなくなるらしい。
お姉ちゃんの電話代を使いたくないので直ぐにこっちからかけ直した。いつもと同じシャキシャキした調子だったが、声のトーンがいつもより少し低い。
お姉ちゃん「なんかようないみたいやわ。しんどいねん」
僕「え、どっか痛いの?」
お姉ちゃん「うーん、痛いとこあるなあ。あっちこち出あるかれへん」
僕「しんどいから?」
お姉ちゃん「昨日な、歩いてる途中でなんか変になってん」
僕「変て、倒れたん?」
お姉ちゃん「歩行器つこてるからな。倒れはせんかった。直ぐ近くに歩いてる人が助けてくれたしな」
僕「あーそれは良かった。あんまり出歩いたらあかんな」
お姉ちゃん「せやろ、ほんでな、先週退院したんやけど、もう一回入院すんねん」
そんな話をした翌日の昨日、フランスにいる妹からメールが来た。
お姉ちゃんが死んだ。
お姉ちゃんの一人娘が僕の妹に連絡したらしい。
一番上に書いた状態がまた戻ってきた。すべてのことが変わりなく進み、僕はすべてのことを変わりなく続ける。その一方で同時に、僕の心の中では何もかも止まっている。音も色も臭いも重力も何もない世界にいる。
今日になって、お姉ちゃんが僕の色紙に描いた水彩画を気に入ってくれたことを思い出した。画家にならなかったことをなんて思っていたのだろうとぼんやり考えていた。
突然ひどい発作のように涙が出てきて、止まらなくなった。
ありがとう、お姉ちゃん。
* * *
注:カバー写真は、お姉ちゃんとよく登った五月山にたくさんあったつつじの花。その蜜を吸うのが楽しみだった。
Tips
チップしてもらえたら、嬉しいです
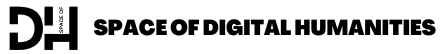






Comments