これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
前書き
本稿は、アルノー・ベルトラン氏(Arnaud Bertrand)の刺激的なポストに触発されて、東アジアから東南アジアにかけての経済と安全保障の現在地を概観する試みである。
まず、ベルトラン氏のポストをみて欲しい。彼はそこで、新華社の報道による中国政府が発表した海南自由貿易港の非常に斬新な経済的実験を簡潔に要約している(ややこしい英文ではないので、読者諸氏はAI翻訳で読んで欲しい)。
そこで、新華社の “Xinhua Headlines: China turns Hainan Island into special customs supervision zone in opening-up drive” という元記事を読んだのだが、これは、ベルトラン氏が紹介しているように「間違いなく今年最大の中国関連ニュースの一つだ」だと思わせるものだった。
これは、中国の小さな島一つの話ではない。この小さな記事の外延は、経済だけに止まらず、東南アジアから東アジアの安全保障策にまで至るものであった。以下で順を追って説明していく。

目次
- 前書き
- 要旨
- 第1章|何が起きたのか――海南で始まった制度変更
- 第2章|海南は例外ではない――中国の「三層構造」
- 第一層:自由貿易試験区――国内制度を試す場所
- 第二層:RCEP――制度を条約として固定する枠組み
- 第三層:一帯一路――制度が回る「物理空間」
- 三層はどうつながっているのか
- 第3章|なぜ中国はCPTPPではなくRCEPを先に選んだのか
- ――「到達点」と「踏み台」の違い
- CPTPPとは何か――自由貿易協定というより「規範の束」
- RCEPとの決定的な違い
- 中国にとっての選択肢は二つしかなかった
- 海南自由貿易港の位置づけがここで明確になる
- まとめ
- 第4章|ASEANはどこに立っているのか
- ――「親中/反中」ではなく「距離の取り方」
- フィリピン:安全保障が前面に出る国
- ベトナム:警戒と依存の同時進行
- シンガポール:中立を制度で支える国
- インドネシア・マレーシア:安定と主導性を重視
- カンボジア・ラオス・ミャンマー:中国依存が顕在化する国
- ASEANは分裂しているのか
- この後、なぜ日本を見る必要があるのか
- 第5章|日本はどこに立っているのか
- ――経済安全保障の名の下で、主権は誰の手にあるのか
- 第6章|台湾有事が起きた場合、この構造はどう揺れるのか
- 結語|主権はどこにあるのか
要旨
海南自由貿易港で始まった制度変更は、中国の一地域開発政策ではない。本稿が示すのは、海南、RCEP、ASEAN、日本の経済安全保障、そして台湾有事が、すべて「有事が起きうる世界において、経済をどう設計し直すか」という一つの問いに収束しているという構造である。
かつて経済は平時を前提に設計されていた。戦争や制裁は例外であり、起きてから対応するものだった。しかし現在では、制裁、金融遮断、物流停止、技術移転制限は、起きうる前提として制度の内部に組み込まれている。経済合理性は市場の効率だけでは完結せず、国家が想定するリスク評価と結びつくようになった。
中国はこの変化に対し、三層構造で対応している。国内では自由貿易試験区や海南自由貿易港で制度実験を行い、地域ではRCEPによって摩擦の少ない共通ルールを固定し、外部では物流や資源の回路を分散させる。海南は、開放と遮断を同時に成立させるための制度的装置である。
ASEANは、中国とも米国とも完全には結びつかず、経済と安全保障を制度的に完全統合しないことで、有事においても断絶を回避する余地を残している。RCEPへの参加は、この「切れにくさ」を条約として確保する選択だ。
日本は異なる道を取った。経済安全保障を制度として組み込み、経済活動を恒常的に安全保障評価の対象とした。その方向性自体は世界的潮流だが、問題は、その安全保障合理性がどこまで日本自身の判断として説明されているかである。この差は、台湾有事が起きた場合に制度の作動として現れる。
問われているのは、中国の意図ではない。日本は、自国の経済を、どの合理性によって、どのように規律するのか。それを自らの言葉で説明できるのかどうかである。
第1章|何が起きたのか――海南で始まった制度変更
2025年12月、中国政府は海南自由貿易港において、島全域を対象とする「特別税関監督区域」の運用を正式に開始した。これは、特定の港湾や工業区に限られてきた従来の自由貿易試験区とは異なり、海南島全体を一つの税関制度として再定義する措置である。
新制度の下では、海外から海南に直接輸入される物資のうち、約74%が無関税の対象となる。これは従来の約21%から大幅に拡大されたもので、対象品目数も約1,900から6,600以上へと増加した。原油、石油化学製品、医療機器、航空関連資材、食品原料など、産業用途の中核となる品目が多く含まれている。
さらに注目されるのは、いわゆる「30%付加価値ルール」である。無関税で海南に輸入された物資であっても、島内での加工や組み立てなどによって付加価値が30%以上生じたと認定されれば、その製品は中国本土へも関税なしで移動させることができる。これは、海南を単なる保管・再輸出拠点ではなく、加工・製造を伴う中間拠点として位置づける設計である。
制度運用上の特徴として、新華社は「第一線」と「第二線」という二重構造を強調している。「第一線」とは、海南と中国の税関区域外(海外)との境界を指し、ここでは通関手続きが大幅に簡素化される。一方、「第二線」とは海南と中国本土との境界であり、本土向けの物資については通常の税関管理が適用される。この構造により、中国は対外的な開放を拡大しつつ、本土経済への影響は管理下に置くとしている。
実際、制度開始当日から海南各地の港湾や空港では動きが見られた。洋浦港では、無関税対象となる石油化学原料約17万9,000トンが到着し、従来制度と比べて約1,000万元相当のコスト削減が見込まれると報じられている。また、海口美蘭国際空港では、海南に拠点を置くチョコレート製造企業が、本土向け出荷を開始したと伝えられている。
中国政府は、この島全域型の特別税関運用について、「高水準の対外開放を進める新たな段階」と位置づけている。無関税、低税率、簡素化された税制を組み合わせることで、物資、資本、人材、データの流動性を高めるとともに、世界的に保護主義が強まる中でも自由貿易を推進する姿勢を示す狙いがあると説明されている。
第2章|海南は例外ではない――中国の「三層構造」
海南自由貿易港で起きている制度変更は、単独の例外措置ではない。中国は過去十年以上にわたり、対外経済の開放を三つの異なる層に分けて設計してきた。重要なのは、それぞれが異なる役割を担い、段階的に接続されている点である。
第一層:自由貿易試験区――国内制度を試す場所
最も内側の層に位置づけられるのが「自由貿易試験区」である。これは2013年に上海で始まり、その後、広東(深圳・広州)、天津、福建、浙江、重慶、四川、陝西など、現在では中国各地に20以上設置されている。沿海部だけでなく、内陸部や国境地域にも配置されている点が特徴だ。
自由貿易試験区の役割は、関税そのものを下げることではない。むしろ、投資規制の緩和、通関手続きの簡素化、金融取引の自由度拡大、サービス分野の開放といった制度変更を、全国一律導入に先立って試す「実験場」である。たとえば、外資規制を原則自由化し例外だけを列挙する「ネガティブリスト方式」や、企業設立手続きの簡略化などは、自由貿易試験区での運用を経て全国に広がってきた。
重要なのは、自由貿易試験区が完全に国内法の枠内にあり、外交交渉を伴わない点である。失敗しても影響は局地にとどまり、中央政府が修正できる。この「失敗可能性」が、制度実験を可能にしてきた。
海南自由貿易港は、この第一層の延長線上にあるが、従来の試験区とは決定的に異なる。特定の都市や工業区ではなく、島全体を一つの制度空間として再設計している点で、自由貿易試験区の「最終形」に近い位置づけにある。
第二層:RCEP――制度を条約として固定する枠組み
第二層に位置づけられるのが、RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership / 地域的包括的経済連携)である。RCEPは、中国が主導して作った枠組みではない。2012年にASEANが提唱し、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランドを含む形で交渉が進められ、2020年に署名、2022年に発効した。中国は創設メンバーではあるが、主導権を握っていたわけではなく、ASEANが中心となって形成された点は明確に認識されるべきである。
RCEPの本質は、関税削減そのものよりも、原産地規則の共通化と貿易手続きの統一にある。これにより、部品や中間財が複数国をまたいで移動するサプライチェーンを、一つのルールで運用できるようになった。企業にとっては、「どの国を経由しても同じ基準で扱われる」ことが最大の利点である。
中国にとってRCEPは、自由貿易試験区で機能した制度の一部を、国内ではなく国際条約として固定する装置である。重要なのは、RCEPがCPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership / 包括的・先進的環太平洋パートナーシップ協定)のような高水準協定ではなく、WTOを土台に実務面を上乗せした「現実的な協定」である点だ。これにより中国は、自国の制度を大きく変えずに、東アジア経済圏を条約ベースで安定させることができた。
第三層:一帯一路――制度が回る「物理空間」
第三層が、一帯一路(Belt and Road Initiative:BRI)である。ここでいう一帯一路は、中国の外交スローガンとして語られるものではなく、制度が実際に機能するための物流・エネルギー・通信といった物理的前提条件の集合として捉える。
一帯一路は、条約や共通ルールというよりも、港湾、鉄道、道路、エネルギー、通信といったインフラ整備を通じて経済活動の空間を作る構想だ。対象地域は東南アジア、中央アジア、中東、アフリカ、欧州にまで及ぶ。
ここでの役割は明確である。いくら制度を整えても、港がなければ物は動かず、電力や通信がなければ投資は定着しない。一帯一路は、自由貿易試験区やRCEPで作られた制度が、実際に機能するための物理的前提条件を整える層である。
三層はどうつながっているのか
この三つは、別々に存在しているのではない。
第一層で制度を試し、第二層で合格した制度を条約として固定し、第三層でそれが回る空間を作る。
この順序は意図的である。
海南自由貿易港は、この三層が重なり合う場所にある。国内制度実験でありながら、RCEP水準の開放を先取りし、一帯一路で結ばれるASEANへのゲートにもなる。だから海南は、単なる地域開発ではなく、中国の対外経済戦略全体を読み解く鍵となる。
第3章|なぜ中国はCPTPPではなくRCEPを先に選んだのか
――「到達点」と「踏み台」の違い
海南自由貿易港の制度設計を理解するうえで、避けて通れないのが、中国がCPTPPではなくRCEPを先に重視した理由である。この選択は、単なる交渉上の成否ではなく、中国が自由貿易をどの段階で、どの水準まで実装するかという戦略判断を反映している。
CPTPPとは何か――自由貿易協定というより「規範の束」
CPTPP(包括的・先進的環太平洋パートナーシップ協定)は、関税削減だけを目的とする従来型の自由貿易協定とは性格が異なる。CPTPPが重視するのは、モノの移動よりも、国家の経済運営そのものに関わるルールである。
具体的には、国有企業への補助金や政府支援の透明化、競争政策の厳格化、労働や環境に関する義務、データの越境移転やローカライゼーション規制の制限などが含まれる。これらは、貿易条件というより、「どのような経済体制を前提とするか」を定める規範に近い。
その意味でCPTPPは、特定地域向けの協定というよりも、グローバルな経済秩序の一つの完成形を提示する枠組みだと言える。
実は、中国は既に 2021年9月 にCPTPPへの加盟を正式に申請している。しかし、中国のCPTPP加盟申請は、三層構造を四層に進化させる宣言ではない。不確実な世界に備え、高規格ルールへの接続可能性を将来の選択肢として保持する行為である。
さらに重要なのは、中国のCPTPP加盟申請は、「参加したい」という意思表示である以前に、「あなたたちが語ってきた自由化は、本当に普遍的なものなのか、相手が中国であっても適用されるのか」という問いを突きつける行為であり、その問いは、日本を含む既存の加盟国に向けられている。
RCEPとの決定的な違い
これに対し、RCEPは、はるかに現実的な協定である。RCEPは、世界貿易機関(WTO)の基本原則を前提にしつつ、原産地規則の共通化や通関手続きの簡素化といった、実務上の摩擦を減らすことに重点を置いている。
RCEPは、参加国の経済体制や発展段階の違いを前提としており、国有企業や補助金、データ統治といった分野には、強い規律を課していない。言い換えれば、RCEPは「どの国でも参加できる最低限の共通ルール」を整える枠組みであり、制度変革を強制しない。
この違いは決定的である。
CPTPPが「経済運営の思想」まで含む協定だとすれば、RCEPは「経済活動を回すための交通整理」に近い。
中国にとっての選択肢は二つしかなかった
中国にとって、CPTPPへの参加は不可能ではない。しかし、それは国内の制度改革を外部規範に委ねることを意味する。国有企業、補助金政策、データ管理といった分野は、中国の政治経済体制の中核に近く、外圧による一括受容はリスクが大きい。
一方、RCEPは、中国がすでに自由貿易試験区で試してきた制度と整合的であり、大きな制度変更を伴わずに参加できた。しかも、日本やASEANといった主要貿易相手国を、条約という形で同じルールに留めることができる。
中国が選んだのは、
- まずRCEPで地域経済圏を安定させ
- その間に国内で制度実験を積み
- 将来的にCPTPP水準に近づく
という段階的戦略である。
海南自由貿易港の位置づけがここで明確になる
この文脈で見ると、海南自由貿易港の役割ははっきりする。海南は、CPTPPが求める高水準ルールをいきなり全国で受け入れる代わりに、限定空間で試す場所である。国有企業、サービス貿易、データ流通といった分野で、どこまで開放できるのかを測るための実験場だ。
つまり、中国は
- RCEPで地域を固め
- 海南で世界水準を試す
という二段構えを取っている。これが、中国の世界戦略と地域戦略の使い分けである。
まとめ
中国がCPTPPではなくRCEPを先に選んだのは、自由貿易に消極的だからではない。むしろ、自由化の水準と順序を厳密に管理しているからこその選択である。海南自由貿易港は、その管理された開放を、次の段階へ進めるための装置として位置づけられている。
第4章|ASEANはどこに立っているのか
――「親中/反中」ではなく「距離の取り方」
海南自由貿易港を含む中国の対外経済戦略を考えるとき、ASEANの位置づけは欠かせない。ASEANはしばしば一括りに語られるが、実際には中国との距離の取り方に大きな差がある。ただし、その違いは「親中か反中か」という単純な二分法では説明できない。
フィリピン:安全保障が前面に出る国
フィリピンは、ASEANの中で最も米国との安全保障関係が可視化されやすい国である。台湾や南シナ海に近い地理条件もあり、有事の際には「前線化」しやすい。一方で、中国との経済関係も無視できず、インフラ投資や貿易では現実的対応を続けている。安全保障では距離を取り、経済では切らないという、最も緊張度の高い立ち位置にある。
ベトナム:警戒と依存の同時進行
ベトナムは中国に対する歴史的警戒心が強く、南シナ海問題でも対立してきた。しかし同時に、サプライチェーンや中間財貿易では中国依存が深い。対米関係も拡大しているが、どちらか一方に賭ける姿勢は見せていない。最も「バランス感覚」を要求される国と言える。
シンガポール:中立を制度で支える国
シンガポールはASEANの中で金融・物流の要であり、米国とも中国とも深い関係を持つ。価値観や法の支配を重視する姿勢は明確だが、対中経済関係を断つことはない。特徴的なのは、立場を感情や政治スローガンではなく、制度とルールへのコミットメントとして表現する点である。
インドネシア・マレーシア:安定と主導性を重視
インドネシアやマレーシアは、ASEANの安定そのものを国益と見なす傾向が強い。中国とも米国とも距離を保ちつつ、域内の分断を避ける役割を担ってきた。特定の陣営に近づくより、ASEANという枠組みが機能し続けることを優先している。
カンボジア・ラオス・ミャンマー:中国依存が顕在化する国
カンボジアやラオスは、中国からの投資や支援への依存度が高い。ASEANの合意形成において、中国に不利な文言を弱める役割を果たすことも多い。ただし、これらの国も完全に中国の代理ではなく、国内政治と経済事情による選択の結果である。
カンボジアやラオスに加え、クーデター後のミャンマーも、中国への経済・外交依存を強めている。ただしミャンマーの場合、それは戦略的選好というより、国際的孤立の結果として生じた側面が大きい(逃げ場がない)。
ASEANは分裂しているのか
このように見ると、ASEAN内部には明確な温度差が存在する。しかし、それは制度的分裂ではない。ASEANは全会一致を原則とするため、強いメッセージは出しにくいが、同時に組織が割れることもない。「まとまらないが壊れない」という性格が、結果として中国にとっても扱いやすく、また扱いにくい存在となっている。
中国はASEANを価値観の同盟相手として信用してはいないが、行動の予測可能性という点では一定の信頼を置いている。だからこそ、RCEPやサプライチェーンといった制度を通じて、ASEANを構造的に結びつけようとする。
この後、なぜ日本を見る必要があるのか
ASEANが示しているのは、経済と安全保障を完全には切り離せない世界で、どう距離を調整するかという現実的な姿である。このASEANの立ち位置を踏まえると、次に浮かび上がる問いは自然に定まる。
では、日本はどこに立っているのか。
ASEANのような「距離調整」は、日本にも可能なのか。
次章では、日本の経済安全保障政策を軸に、この問いを検討する。
第5章|日本はどこに立っているのか
――経済安全保障の名の下で、主権は誰の手にあるのか
日本は主権国家である。少なくとも形式上はそうであり、そのこと自体を疑う者は多くない。しかし、経済安全保障という制度が急速に整備される現在、日本はその主権を、どこまで実質的に行使できているのだろうか。本章で問うのは、日本の経済安全保障政策が正しいか誤っているかではない。それが主権国家としての日本自身の判断として設計・運用されているのか、という一点である。
日本では近年、経済安全保障が法制度として本格的に整備され、経済活動は恒常的に安全保障評価の対象となった。重要物資の指定、基幹インフラの審査、先端技術やデータの管理、特許の非公開制度などは、もはや例外的措置ではなく、平時から常態的に運用される枠組みとなっている。経済は、市場の合理性だけで動く領域ではなくなり、国家の安全保障判断を前提とする制度空間に組み込まれた。
このこと自体は、国際的に見て特異ではない。制裁、金融遮断、物流停止、技術移転規制が頻発する現在、経済を平時のみを前提として設計することは困難であり、多くの国が同様の制度化を進めている。したがって、経済安全保障が経済に「侵入」したことそのものを問題視するのは、論点を誤る。
問題は、その中身である。
日本の経済安全保障は、主権国家としての日本自身の脆弱性評価と戦略目標に基づいて、どこまで主体的に構成されているのか。実際には、半導体、先端技術、サプライチェーン再編といった中核分野において、日本の制度運用は米国の対中戦略と高度に同期した形で進められている。この事実自体は否定できないし、同盟関係の中で一定の合理性を持つ選択であることも否定できない。
しかし、ここで問われるべきなのは、その合理性が日本固有の判断として、どこまで言語化され、社会的に引き受けられているのかという点である。米国の戦略と一致していること自体が問題なのではない。問題は、それが日本自身の戦略として説明されないまま、「安全保障だから」という言葉で制度化されていく過程にある。
この状況は、「日本はアメリカの植民地なのか」「対米自立は可能なのか」といった、SNS上で氾濫する言葉を想起させるかもしれない。しかし本稿は、そうした感情的な二分法に与しない。問うべきなのは、従属か自立かという抽象的なスローガンではなく、主権国家としての日本が、経済安全保障の内容を自ら決定し、その決定に責任を持っているのかという、具体的で制度的な問題である。
市場合理性が否定されたわけではない。価格、効率、競争力といった基準は、依然として経済判断の基礎であり続けている。ただし、それだけでは最終判断にならなくなった。安全保障合理性は、市場合理性に取って代わったのではなく、それを拒否し得る上位条件として制度の中に組み込まれた。だからこそ重要なのは、その拒否権を、誰の合理性に基づいて行使しているのか、という点である。
もし日本が、主権国家として経済安全保障を運用するのであれば、どの分野で制約を受け入れ、どの分野では接続を維持するのか、その線引きを日本自身の言葉で示さなければならない。それができないまま制度だけが積み上がれば、日本の経済は結果として、他国の戦略に強く規律された形で配置され続けることになる。
これは反米でも親中でもない。
主権国家としての制度設計の問題である。
日本の経済安全保障が本当に「日本のもの」であるのかどうか。その問いから目を逸らさないことこそが、現在の日本に求められている。
しかし、この問いは抽象的な理念の問題にとどまらない。
経済安全保障が「誰の合理性」によって設計されているのかという違いは、平時には見えにくいが、有事という条件が与えられた瞬間に、制度の作動として可視化される。どの国と経済関係が遮断され、どの回路が残され、どの選択肢が自動的に閉じられるのか――それらはすでに、政策判断ではなく制度配置の結果として決まっている。
第6章|台湾有事が起きた場合、この構造はどう揺れるのか
前章で問うた「主権は誰の手にあるのか」という問題は、理念や態度の問題ではない。それは、特定の条件が与えられたときに、制度がどのように作動するかという、きわめて具体的な問題である。台湾有事という仮定は、日本の経済安全保障がどの合理性に基づいて設計されてきたのかを、政治的意思決定ではなく、経済の動きとして可視化する条件を与える。
ここまで見てきた海南自由貿易港、中国の三層構造、ASEANの距離調整、日本の経済安全保障は、いずれも平時の政策選択として語られてきた。しかし、これらの制度配置は本質的に、「台湾有事が起きた場合に何が起きるか」という問いに対する事前の回答として設計されている。
仮に台湾海峡周辺で軍事的衝突が発生した場合、最初に動くのは軍事同盟や外交声明ではない。先に反応するのは、金融、保険、物流といった経済インフラである。紛争リスクが顕在化すれば、船舶保険料は急騰し、場合によっては付保自体が停止される。航空・海運は危険水域を回避し、金融機関は制裁リスクを理由に取引を止める。これは政治判断を待たず、市場と制度が自動的に作動する段階である。
この時点で、国際経済はすでに「部分的遮断」に近い状態に入る。全面的な制裁が発動されていなくても、経済活動は実質的に大きく制約される。台湾有事とは、まずこの形で現れる。
日本は、この局面において極めて分かりやすい位置に置かれる。前章で見たように、日本では経済と安全保障が制度として結合しており、輸出管理、技術移転、投資判断は、有事が発生すれば政治判断を経ずに連動する構造になっている。これは、日本が意図的に「参戦」するかどうかとは別の問題である。制度の配置上、日本は台湾海峡をめぐる緊張が高まった段階で、経済的にも遮断される側に自動的に分類されやすい。
ASEAN諸国は、同じ状況でも異なる揺れ方をする。多くのASEAN諸国では、経済と安全保障が完全には制度的に結合しておらず、制裁や遮断への対応は国別判断に委ねられる余地が残されている。そのため、有事が起きた場合でも、経済関係が一斉に断ち切られるとは限らない。揺れは生じるが、完全な分断には至りにくい。この「切れにくさ」こそが、ASEANが中国にとっても、また米国にとっても、無視できない存在であり続ける理由である。
中国側の制度設計は、こうした差異を前提に組み立てられている。台湾有事が起きた場合、中国は日本や米国を経由する調達や金融ルートの多くを失う可能性が高い。その事態を想定したとき、海外との接続をどこに、どのような形で残すかが決定的に重要になる。海南自由貿易港は、この問いに対する制度的回答である。
海南では、海外との通関を最大限に緩めつつ、本土との間には明確な管理境界を設けている。無関税で輸入した原材料を島内で加工し、一定の付加価値を加えた上で本土に流すという設計は、単なる自由化政策ではない。特定の国や政治関係に依存せず、有事下でも経済を回し続けるための回路を国内に内製化する試みである。
ここで重要なのは、中国が台湾有事を「起こすため」に海南を整備しているのではないという点だ。むしろ、有事が起きた場合でも国家と経済が急激に機能不全に陥らないよう、平時のうちから制度を組み替えている。その意味で、海南自由貿易港は軍事戦略ではなく、経済統治の問題として理解されるべきである。
このように見ると、台湾有事は未来の出来事ではなく、すでに各国の制度設計の中に前提条件として書き込まれている。日本、ASEAN、中国は、それぞれ異なる形でこの前提に対応しており、その違いは、有事が起きた瞬間ではなく、起きる前から制度の中に現れている。
海南自由貿易港が示しているのは、中国の野心や意図ではない。有事前提の世界において、どのように開放を維持し、どこで遮断を受け入れるのかという、現実的な統治上の選択である。そしてその問いは、日本にも同じ形で突きつけられている。
結語|主権はどこにあるのか
主権は、意思を表明することによって完結する概念ではない。どの判断を、どの制度を通じて実行し、その結果として生じる帰結を誰が引き受けるのかまでを含めて、はじめて具体的な意味を持つ。主権とは、理念や態度に留まるものではなく、制度設計とその作動において測られる能力である。
本稿で見てきた海南自由貿易港、中国の多層的な対外経済構造、ASEANの距離調整、日本の経済安全保障は、いずれも「自由か統制か」という二分法では捉えきれない。それらは、有事が起きた場合に経済がどのように動くのかをあらかじめ織り込んだ制度的選択であり、主権がどの位置で発動し、どの局面で制限されるのかを示している。
経済安全保障とは、自由を放棄することでも、対立を選ぶことでもない。それは、どの分野で遮断を受け入れ、どの分野で接続を維持するのかという線引きを、平時のうちに制度として書き込む作業である。その作業を自国の判断として行えているかどうかが、主権の実質を左右する。
日本の場合、経済安全保障はすでに制度として整備され、経済活動は恒常的に安全保障評価の対象となっている。問題は、その制度が存在することではなく、その内容が日本固有の脆弱性評価や戦略目標として、どこまで言語化され、社会的に引き受けられているのかという点にある。他国の戦略と一致しているか否かではなく、それが日本自身の選択として説明されているかが問われている。
台湾有事という仮定が示したのは、主権が「あるかないか」を争う問題ではない。制度が作動する瞬間に、どの選択肢が自動的に閉じられ、どの回路が残されるのか。その結果を誰が引き受けるのかという、きわめて実務的な問題である。主権は、そこで初めて可視化される。
誰に従うか、誰に抗うかという単純な図式では、この問題は理解できない。必要なのは、どの判断が、どの制度を通じて、どの結果をもたらすのかを、自らの言葉で説明し続ける能力である。日本が主権国家であり続けるためには、その能力を制度として保持し続けられるかどうかが問われる。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
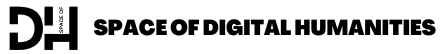











Comments