これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
スコット・リッター氏は、ロシアから帰国した直後に、この記事で何をしてきたかを報告しています。そのタイトルは、
Citizen Diplomacy
Russophobia is a disease of the mind. Citizens Diplomacy is the cure.
Scott Ritter
Aug 23, 2025
市民外交
ロシア恐怖症は精神の病である。市民外交がその治療法だ。
スコット・リッター
2025年8月23日
前回の記事、【Overseas-38】「スコット・リッター:ロシア再訪」で彼が説明した通りのことをロシアでやってきて、それを公に報告するのがこの記事です。公費で外遊に行った国会議員が報告書を公に発信したケースが日本にあるのかどうか知りませんが、私自身は見たことがありません。リッター氏を見習うべきでしょう。
リッター氏は、この記事を大原則を確認することから始めます。具体的には、国民と政府の関係の原則とななんであるか、良き市民/国民であるとはどういうことかということについてです。
その次に、彼を市民外交に向かわせる動機となっているアメリカにおけるロシア嫌悪(Russophobia)の問題について、前回の記事よりも詳しく描写しています。例えば、次のような一節があります。
ロシア嫌悪は、ロシアの現実について虚偽を広め、それによって恐怖を生み出すことで、アメリカ国民の無知を利用するよう仕組まれている。そしてその恐怖は、我々が選出した人々によって利用され、ロシアを永遠の「お化け(bogeyman)」として描き出す政策を支えるために用いられる。
彼が、Citizen Diplomacy と呼んでいる行動は、この無知に基づくロシア嫌悪(Russophobia)を解消することを目的としているのです。アメリカ人がロシア人をもっと知る、それが長い目で見れば、アメリカ政府の愚策に次ぐ愚策という連鎖を断ち切る力になるというのが彼の考えです。
そんなのんきなこと言ってんのかと思われる人もいるかもしれませんが、外交は国家の政府組織と政府組織の間だけで成立していると考えるのは大きな間違いです。リッター氏はそれを彼のキャリアの上で体得したのだろうと思います。
国連組織の中で長く働いていると、だんだん現場の活動から離れて、組織内ではマネジメント、組織外では交渉ごとの割合がどんどん大きくなります。毎月のようにNYからどこかの国へ飛ぶことになるのですが、現地に着くと、総称してUN Diplomat と呼ばれます。しかし、実際の仕事はそのような裃(かみしも)を脱いだところで始まります。人間として知り合い、フラットに話ができる関係にならないと、何も始まりません。むしろ肩書きと肩書きがせめぎ合う公式の外交の場は、単なるショータイムなのです。すべてはその外で終わってます。
だから、リッター氏が citizen diplomacy というフレーズで言いたいことはよく分かります。彼はここまで悪化した米露関係を改善するには土壌を入れ替えないと考えているのだろうと思います。土壌というのは、一般人のロシア観です。このフレーズを一応「市民外交」と訳してますが、日本語で「市民」というと何か特別なもののように僕は感じるので、あまり良い訳だと思ってません。リッター氏が言うcitizen diplomacy とは「一般人同士のつきあい」のようなニュアンスだと思います。土壌改善はそこでのみ可能になる。公式外交では無理です。
同じようなことを日本は、ロシアだけでなく、中国や韓国とやらなければならないと思います。あまりに深い無知にわれわれ日本人は蝕まれている。
それでは、リッター氏の報告書をどうぞ。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
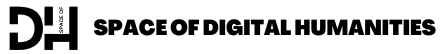




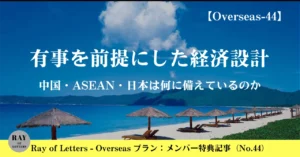
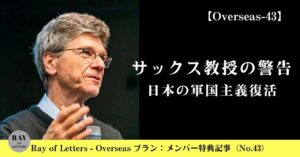
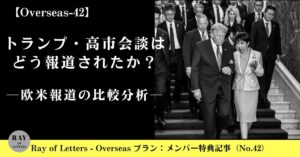
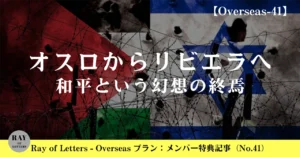
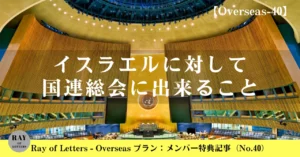
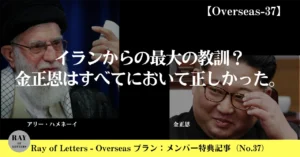
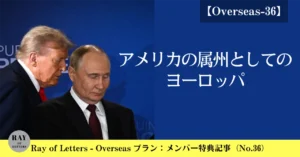
Comments