これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
[7,674字]
この記事の内容は、下の動画で見ることが出来ます。
「2000年、日本の経済はASEANの8倍でした。今は1.3倍です。」
という言葉が、このインタビューに出てくる。日本経済の凋落は誰でも分かっていることだが、こんなに短期間にこれほどの落下はどうやれば可能になるのかといまさらながらに考えてしまう。
ASEANが急成長したからだと言う人はいるだろう。それも正しい。しかし、日本側の衰退との掛け算の結果というのが真実に近いだろう。
これは、シンガポールの著名な外交官、学者、作家であるキショール・マブバニ(Kishore Mahbubani)のインタビューを書き起こしたものだ。彼は、アジアの地政学と国際関係に関する専門家として広く知られている。
彼は、1971年から2004年までシンガポール外務省で勤務した。1993年から1998年まで国連大使を務め、2001年と2002年には国連安全保障理事会の議長を務めた。
現在はシンガポール国立大学(NUS)同大学の特任教授(Distinguished Fellow)。
このインタビューの焦点は日本ではない。マブバニ氏は、長期的に、かつ急激に変わってきた世界像を提示しようとしている。彼は、エビデンスを上げて、穏やかに世界の力関係に何が起きているかを示す。
それは、西から東へと力がシフトしているということだ。彼は、それを象徴的に、G7は黄昏(Sunset)の組織、BRICSは夜明け(Sunrise)の組織と表現している。
その現実を基にして、今後、西洋がどう振る舞うべきかを彼は諭している。決して横柄な態度ではないが、西洋にへつらう卑屈さも微塵もない。アジア人として誇りをもてる態度に感心するし、本邦を振り返り、情けない気分になる。
日本人は、極めて狭量な、国内的党派性を乗り越えて、世界の現状を直視するべきだ時だ。そうすれば、「横柄でも卑屈でもない」振る舞い方が出来るようになるかもしれない。
話題が多岐にわたるので、小見出しをつけた。以下の目次は、その小見出しです。
目次
- 西から東への力のシフト
- 米国経済と中国経済の比較
- アジアの成長とCIA諸国
- 中産階級と欧米の比較
- 欧州の立場と対等な関係
- 欧州の戦略的アイデンティティ
- アジアの歴史と文化的つながり
- 中国との関係とベトナムの例
- 日本の経済とアジアのプラグマティズム
- 欧州の長期戦略とアフリカの人口爆発
- 欧州の過去と謙虚さの必要性
- アジアの多様性とASEANの役割
- 中国とインドの関係とプラグマティズム
- BRICSと米国の投資
- アジアの複雑さと多文明世界
- 欧州の無知と米中競争
- 気候変動と欧州のリーダーシップ
1:西から東への力のシフト
キショール・マブバニ:
西から東への力のシフトは疑いようがなく、アジアの大国と欧州の大国の相対的な地位は大きく変化しています。
一つの統計から始めましょう:1980年、欧州連合の合計GDPは中国の10倍でした。
今日、欧州連合のGDPは中国とほぼ同じ規模であり、2050年までには欧州連合は中国の半分の規模になるでしょう。
欧州連合が中国の10倍の規模から中国の半分の規模になることは、力がアジアに劇的にシフトしていることを示しています。
2:米国経済と中国経済の比較
インタビューアー:
同時に、米国経済は非常に好調です。それは依然として世界最大の経済です。
キショール・マブバニ:
2000年、米国の経済は中国の8倍でした。今では1.5倍にすぎません。
したがって、米国と中国の相対的な関係は変化しました。
欧州経済とは異なり、米国経済が好調で堅実に成長していることに完全に同意します。
しかし、予測を求められれば、2050年までには中国経済が米国経済を上回ると言います。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
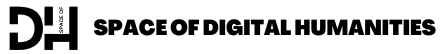




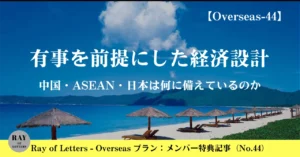
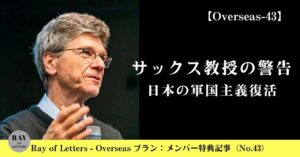
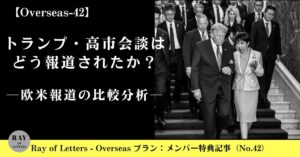
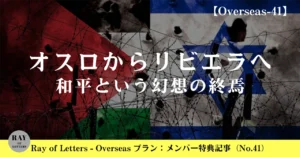
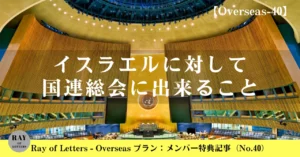


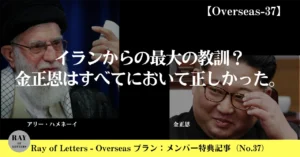
Comments