これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
埴輪好きな方、全員集合してください。今回はほんとに旅になってしまった。埴輪と時空間を經巡る旅です。
埴輪が気になり始めたのは、小学校の低学年の頃だったと思う。正確なことは何も覚えていないが、学校で習ったとか、どこかの博物館へ行って見たとか、そんな記憶はない。当時の自分の生活環境から考えて一番あり得るのはこれだと思うことが一つだけある。
I. 僕の埴輪
小学校の裏門にいた物売り達
それは、小学校の裏門を出たところに、やってくる物売りのことだ。日によっていろんな物売りが路上に売りものを並べて、学校から出てくる小学生に売っていた。今から思えば、小学生が持ってるお金などしれているのに、商売になったのだろうかと思うが、なぜか彼らはやってきた。
日によって、異なる物売りがやってきた。必ず一種類の物売りしか来ないので、夜店のようにいろんな物売りが賑やかに並んでいるような風景とは違う。
どんな物売りか全部は覚えていないけど、少し覚えているのは、例えば、針金でいろんな形のものを作って売る人。それは動物だったり、乗り物だったり、鉄砲だったり、色々だった。出来上がった針金細工を路上に並べ、それと同じものを物売りはせっせと作っていた。
小学生に人気のあったのは、針金で作った鉄砲(ピストル)に輪ゴムを組み合わせて、パチンと「撃てる」仕組みがついているやつだった。輪ゴムが飛ぶような仕組みにはなっていたと思うがよく覚えていない。
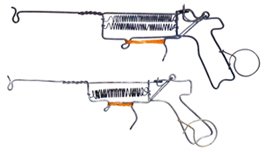
竹細工の物売りもよく来ていた。ザルやツボのような形のものを作っていたと思うが、そんな実用的でない動物の形をしたものもあった。

泥で作ったレリーフのようなものに金粉とか銀粉を塗りたくったものを売る物売りもいた。一番大きいやつは(と言っても手のひらサイズだが)、鬼の顔でそれが黄金色に輝いていた。小学生の僕はそれに畏怖ようなものを感じていた。
給食センター
町の中心にあった、その小学校には出来たばかりの「給食センター」という当時としては”進んだ”ものがあり、そんな学校に通う小学生の自分に誇らしい気分があったのを覚えている。
給食センターで出来た温かい給食は楽しみだった。好きなメニューは、カレー、いろんな野菜が入った煮込みうどん、糸こんにゃく多めのすき焼きのようなもの、鯨の竜田揚げだった。この給食には、食パン2枚に、マーガリンが一個とみかんの切れ端のようなものが入った甘いものがついていて、僕はそれも好きだった。その甘いものがマーマレードと呼ばれているものだと知らなかった。生まれて初めてマーマレードを食べたのが小学校の給食だったのだ。
幼稚園の時は、脱脂粉乳をブリキのドラム缶のようなものに付いた蛇口から、園児がブリキのお茶碗に一人ずつ入れてもらっていた。それがランチだった。そこから「給食センター」への飛躍は大きかった。今だから白状するが、それが未来からやってきたようなわくわく感を持っていた。
そう言えば、幼稚園では栄養の補助のために、m&m’s のチョコレートのような形の茶色の飴のようなものを毎日食べさせられていたと思うが、それがいつまで続いていたのかは忘れた。あれは何だったのかな。
極貧と成金の間
僕が小学校に入学したのは、1964年(昭和39年)だったから、戦争が終わって19年経った頃だ。脱脂粉乳と栄養補助飴に残る極貧の跡と、給食センターがまとう高度成長の兆しの間に嵌まっていたのが、僕の年代の子どもたちだった。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
1960年(昭和35年)、僕が2歳の時に所得倍増計画がぶち上げられ、1964年(昭和39年)、僕が小学校へ入学した時に東京オリンピックがあり、1966年(昭和41年)、僕が小学3年生の時、ビートルズが来日した。日本は極貧から成金へまっしぐらに向かっていた。
小学校の3、4年生の時だったと思うが、転校生がやってきた。おとなしく、あまり喋らない男の子だった。
その小学校では普段は給食センターで調理される給食を食べていたが、運動会や、学芸会や、遠足などの催しものがある時は給食がなかった。何の催しものだったか忘れたが、そんなある日、その転校生がはにかんだ笑顔をしながら、教室でお弁当箱を開けた場面を覚えている。その中には、胡瓜とニンジンのかけらのようなものがころんと入っていた。それだけだった。彼は恥ずかしそうな笑顔は絶やさず、うちには何にもないというようなことを言っていた。僕は胡瓜のかけらを一つちょうだいと言って、自分の卵焼きのかけらと交換した。
僕はお弁当の日が嫌だった。母の作るお弁当はいつもオムレツ、と言えば聞こえはいいかもしれないが、白いご飯の上にぺろっと一面に卵の焼いたものがのっているだけだった。お弁当箱に色んなおかずが入ってる他の子が羨ましかった。
母は忙しくてお弁当を作る時間がなかったのか、あるいはいろんな食材を買うお金がなかったのだと長い間思っていたが、ずっと後になって、大人になってからだが、ひょっとして母には小学生のお弁当というイメージがなかったのではないかと思い始めた。いろんなものが少しずつ華やかに詰め合わせられたお弁当箱。昭和10年生まれの彼女の人生にそんなものはなかったではないか。
戦争が終わった時、母は10歳だ。母と父は戦後の食べ物がなかった頃の話をよくしていた。具がなくて水っぽい”すいとん”に芋の蔓を入れて野菜の足しにしていたと言っていた。”白いご飯”なんてめったに食べられなくて主食は芋だったそうだ。
昔からある言い伝えなのか、母が勝手に作った話なのか分からないが、米粒を残すと目がつぶれると母はよく言っていた。お百姓さんが一生懸命作ったお米を残してはいけないと。
小学5年の時に行った林間学校の時のことだったと思うが、生徒みんなが大広間で昼ごはんを食べていた。僕は母が言ったことを忠実に履行していたので、最後にどんぶりにくっついた米粒を一つずつ箸でつまんで食べていた。それを見た担任の先生が、ちょっと驚いたような顔をして、いつもそうやって食べているのかと訊いたのを覚えている。僕は、その時に初めて、米粒を全部食べない人もいるということを知った。そうやって、子どもの視界は少しずつ広がっていった。40代半ばくらいまで、僕は食べ物を残すことが出来なかった。
米粒だけでなく、「出されたものは全て食べる」という母によってもたらされた教義は、僕の中にずっと残り続けた。美味しいものは好きだし、食べ物による健康も考えるが、美味しいからとか、身体に良いからという理由をつけられると、途端に食欲がなくなる。食べることに理由をつける不遜さを感じてしまう。グルメなどという言葉には嫌悪感しかない。
話が逸れた。
終戦直後、10代の女性である母は田舎に買い出しに言って恐ろしい目にあったことも話していた。そこに大人の男の影を感じたが、詳しいことは知らない。7年間の占領時代が彼女の10代の青春だった。
母にとっては、お弁当箱一面を覆うオムレツはとてもご馳走だったというのが正解かもしれない。そんなすごいご馳走を子どもに食べさせると。上に書いたように、それに気がついたのは大人になってからだった。この親子の思いのすれ違いも、やはり極貧の跡と成金国家の兆しの二つがオーバーラップしながら、日本が変わっていった時代の産物だったのだと思う。
転校生の話に戻ると、彼はずっと大人しく喋らない転校生のままだったが、僕はその転校生と仲良くなっていった。ある日、彼の家に行くことがあった。はっきり覚えているわけではないが、だいたいの位置は今でも分かる。新町商店街にあった映画館の裏の辺りだ。彼の家は玄関の引き戸を開けると、小さい土間のような空間があり、その先に薄暗い畳の部屋が一間あった。他には何もなかった。
そのような作りの家を訪れたことが以前にも一度あった。同級生の男の子なのだが、とても小さい子で、「うちは貧乏やから」というのが口癖だった。彼は歳の離れたお姉さんと二人で住んでいた。両親が亡くなったのか、他の事情があっていっしょに住んでいなかったのかは知らない。彼の家に行った時も、玄関の引き戸を開けると薄暗い転校生の家と同じ風景だった。
お弁当が必要な時、この同級生が持ってくるのは、いつもおにぎりが一つだった。しかし、とても大きな、横幅が20センチ以上ありそうなおにぎりで、全面が海苔で包んであった。他におかずはない。それを小さい彼が両手で持って食べる姿が記憶に残っている。
さて、転校生の家に行った時にどんな話をしたのかなんてまったく覚えていないのだが、一つだけ鮮烈に覚えていることがある。彼のお父さんの仕事が竹細工だということを知ったことだ。学校の裏門で竹細工を作って売ってる人だった。自分の父はサラリーマンだったので、竹細工の人だと!すごい!と思ったのだろう。なんかセレブにあったように僕は高揚した。
それから、しばらくして彼はまたどこかへ転校していった。一学期くらいしかいなかったような気がする。それっきり何の音沙汰もなく、彼のことは長い間忘れていた。それから、おそらく20年近く経って、僕は『忘れられた日本人』(宮本常一)と遭遇し、日本の民俗学にどっぷりとはまる時期を迎えた。昔の日本人への興味が爆発し、その手の本を片っ端から読み始めた。
そして、当然サンカに出会う。山の民、流浪の民、竹細工。えっ?あっと思った。あの転校生はサンカの末裔に違いないと僕は一瞬で決めつけた。街に降りて来たサンカ。居場所のないサンカ。貧乏なサンカ。ほぼ全て勝手な想像なのだが、僕にとっては、あの転校生はサンカの末裔でなければならなくなった。それから『風の王国』(五木寛之)を読んでは、あの転校生どうしてるかなあと僕は想像に浸るようになった。
歴史の教育
横道にそれ過ぎて、なかなか埴輪に戻れない。まず物売りの話に戻ると、ちょっと今では想像つかないと思うが、物売りの中に百科事典を売る人がいた。これは書きながらも顔がほころんでくるのだが、本当に小学校の裏門の前でそんなものを売っていたのだ。まず子どもに百科事典を欲しがらせ、家に帰って親にねだらせる。そしてセット売りの契約を取るというビジネスだったのではないかと思う。ウィキペディアを見ると、その頃の日本は百科事典ブームだったようなのだ。
さらに昭和期の高度経済成長を経ると1960年代頃には各家庭に分冊の百科事典が置かれているのは珍しい風景ではなくなり、大衆化を果たした。(中略)各社から次々と百科事典が刊行され人々もそれを求めたこの時期を指して、百科事典ブームと呼ぶ。
ウィキペディア
訪問販売が勢力的に行われていたようで、小学校の待ち伏せ販売はその派生系だったのだろう。
こうした百科事典は書店の店頭販売だけではなく、セールスマンによる訪問販売も盛んに行われた。1970年前後には、強引な百科事典の販売が社会問題となり、このことがきっかけに夜間訪問の禁止など訪問販売のルールの原型が作られた。
ウィキペディア
百科事典じゃない本も売りに来た。大判のカラー写真がふんだんに入ったツルツルの紙の地理とか歴史の月刊誌だった。当時そんな本はほとんど見たことがなかったと思う。僕はキラキラした本を手に取り、そこで立ち読みか、座り読みをしていた。この物売りの何度目かの訪問の後、意を決して僕は母にこの歴史のシリーズの購読を頼んだ。この物売りの作戦は成功したのだ。
その翌月から毎月一冊、大きくてカラフルでキラキラした歴史の本が届くようになった。福岡の百姓が田んぼで「漢委奴國王」と書かれた金印を発見した話を興奮して読んだのはよく覚えている。「かんのわのなのこくおう」と読む不思議さにも感動していた。
やっと辿り着いた。僕が初めて埴輪に出会ったのは、おそらく、いや確実にこの歴史月刊誌だったはずだ。その頃の僕の極小の知的世界を考えると、それ以外の可能性がない。
その一冊にある埴輪の姿形が頭に焼き付いた。土偶もなかなか好きなのだが、埴輪には、こいつ生きてるんちゃうかと思わせる生命感を感じた。世の中の土偶派には悪いが、土偶には宇宙人的な冷たさを感じた。埴輪からはもっと生き生きとした人間っぽいものを感じたのだった。僕は断然、埴輪派になった。

II. 和辻哲郎の埴輪
和辻哲郎の『人物埴輪の眼』を青空文庫で見つけた時、速攻で読んだ。短い論考なので、すぐ読み終わる。
僕は感嘆した。こやつ、出来る奴だと思った。小学生の僕が持った謎の高揚感が全部文字になって説明されていた。和辻哲郎、恐るべし。
その部分を書く前に、和辻による埴輪の説明を少し書いておく。
埴輪の稚拙さ
埴輪というのは、古墳時代の5世紀頃の、とてもシンプルで稚拙な造形物だ。この「稚拙」という点が第一の大きなポイントになる。
埴輪の稚拙さは、土偶の「怪奇性」とはまったく違うということを和辻は指摘する。僕が土偶は宇宙的と感じていたことが、和辻のいう「怪奇性」だと思う。
怪奇性というのは、原始芸術に特有なものらしい。和辻は言う。
わが国でそういう原始芸術に当たるものは、縄文土器やその時代の土偶などであって、そこには原始芸術としての不思議な力強さ、巧妙さ、熟練などが認められ、怪奇ではあっても決して稚拙ではない。それは非常に永い期間に成熟して来た一つの様式を示しているのである。
縄文人も侮れない。土偶は、彼らの構想を練りに練った末の産物だったのだ。
ところがだ。これが定住農耕生活の始まった弥生時代になると、ころっと変わってしまう。土器の形も、模様も、怪奇性を脱して非常に簡素になったのだ。縄文から弥生への移行は、造形芸術では怪奇から簡素への移行であったと。

人物や動物の造形は、銅鐸や土器の表面に描かれた線描においてにおいて現われているが、これは縄文土器の土偶に比べてほとんど足もとへもよりつけないほど幼稚なものである。
と和辻は言う。洗練と幼稚化は、人類史のいろんな側面でも繰り返されて来た。我々は一直線に輝く未来に向かって進んで来なかったし、これからもそうだろう。
そんな弥生式文化の時代が三世紀くらい続いた後、古墳文化が現れたのだから、埴輪は縄文土器の伝統とはまったく独立に作り始められたと和辻はいう。つまり、埴輪と土偶は兄弟姉妹ではなかったのだ。埴輪の稚拙さと土偶の怪奇性の間には全く繋がりがない。
古代の造形芸術の変遷を整理しておくと、
◽️縄文時代:怪奇(土偶)
◽️弥生時代:幼稚
◽️古墳時代:稚拙(埴輪)
ということになる。
埴輪の非写実性
次に和辻があげる埴輪の第二のポイントが僕の脳天で炸裂した。それで今回この本を取り上げようと思ったのだった。和辻は言う。
「埴輪の造形は必ずしも人体を写実的に現そうなどと目指してない」。
埴輪は円筒形に何か「意味ある形」をくっつけただけで、円筒形を人体に改造したわけではないのだ。だから、四肢はたいてい無造作に取り扱われてる。両足はほぼ無視され、両腕は何かを持ってたり、踊ってたりすることを示す時だけつけられるが、写実的に表現しようという意図は全然見られない。
では、「意味ある形」とは何なのか?和辻は、まず「甲冑」の例を出す。「甲冑」を円筒上の人物に着せた場合は、四肢とは段違いの細かい注意をもって表現されている。鉄板の堅い感じや、鉄板をつなぎ合わせている鋲がかっちり並んでいるとこまで表現されている。古墳人が、人体よりもこういう鉄の武器にはるかに強い関心を持っていたことを示すと和辻は言う。

しかし、和辻は「意味ある形」の中でも、もっとも重い意味を担っていたのは何と言っても「顔面」だと言う。だから、埴輪の顔面が他の部分と著しく異なった印象を与えるのは当然だと。顔面にある、眼、鼻、口、頬、顎、眉、額、耳などの中でも、眼が非常に重大な意味を担っている。原始的な造形において眼が重大な役割を果たしているのは、埴輪に限らず、南フランス(アルタミラのことか?)の洞窟にある動物画でもそうであるらしい。
埴輪の眼は無造作にくり抜いた穴だ。写実的に現そうとした気配は全くない。しかし、この二つの穴は、魂の窓としての眼の役目を十分に果たしていると和辻は書く。そう、そうなんですと僕は和辻の叙述にどんどん引き込まれていった。古墳時代の人は、この無造作に開けられた二つの穴が埴輪の顔面に生き生きとした表情をもたらすことをよく心得ていたのだ。
もし、この眼が写実的に作られていたら、どうだろう?少し遠のけば、はっきりと見えなくなるだけだ。しかし、この空洞の穴は、
そばで見れば粗雑に裏までくり抜いた空洞の穴に過ぎないのであるが、遠のけば遠のくほどその粗雑さが見えなくなり、魂の窓としての眼の働きが表面へ出てくる。それが異様な生気を表してくるゆえんなのである。
やられた。完全KOだ。小学生の僕が埴輪に見たのは、魂の窓だったのだ。この後に、和辻はご丁寧にとどめを刺しにくる。
こう考えてくると埴輪の人形の持っているあの不思議な生気のなぞが解けるかと思う。
はい、解けました。仰る通りです。
造形芸術と精神生活
付け足しになるが、この論考の中で、和辻は眼に見えるものとしての造形芸術とその背後にある人間の精神生活との関係に言及することが二箇所ある。
一つは、埴輪の技術が稚拙であっても、「人」を顔面によって捉えようとする態度は稚拙ではないということを言っているところだ。埴輪を作っていた古墳時代の人も技術を学べば、それに乗って急に溢れ出る何かが背後にあると、和辻という。その背後にある何かは古墳時代に生きた日本人の精神生活のことだと思う。それ故に、ほんの一、二世紀後に、彫刻としては全く段違いの推古仏を作り得たことがさほど不思議ではないと締めくくる。
古代の造形芸術の変遷をもう一度まとめるとこうなる。
◽️縄文時代:怪奇(土偶)
◽️弥生時代:幼稚
◽️古墳時代:稚拙(埴輪)
◽️飛鳥時代:超絶技巧(推古仏)

もう一つは、この論考のかなり最初の方に出てくる。古墳時代は、紀元三世紀ごろから七世紀ごろまで続いたというのが通説だ。人物埴輪が多く現れるのは紀元五世紀頃だ。
この時代、応神、仁徳朝の朝鮮関係が中心になっているが、それに関して、和辻は次のように書いている。
あれほど大きい組織的な軍事行動をやっているくせに、その事件が愛らしい息長帯姫(おきながたらしひめ)の物語として語り残されたほどに、この民族の想像力はなお稚拙であった。
これが、人物埴輪を作っていた時代の日本人であった。奈良時代最初期に成立する日本書紀や古事記は、突然誰か一人が書いたものではなく、その前の飛鳥時代、つまり埴輪が全盛の古墳時代に書かれたものの集積が土台になっている。この辺のことを和辻は次のように書いている。
たとい稚拙であるにもしろ、その想像力が、一方でわが国の古い神話や建国伝説などを形成しつつあった時に、他方ではこの埴輪の人物や動物や鳥などを作っていたのである。
つまり、言葉による物語と、形象による表現とは、かなり異なってもいるが、同じ想像力の働きである、と和辻は考えている。埴輪を作っていた人たちが語っていた話が溜まり溜まって飛鳥時代の日本書紀や古事記という形になったと言えるかもしれない。
最後の最後に書くが、現代日本における言葉の破壊は、精神生活の破壊であることをよく物語っているように思える。また近代芸術にしろ、市井の伝統の中に佇む芸術にしろ、現代日本による徹底的な軽視と破壊が進むのも精神生活の破壊によるものと見える。
1000年先くらい未来の和辻哲郎が今の日本を発掘したら、醜い造形芸術と精神生活の荒廃をまた発見するのではないだろうか。
END
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
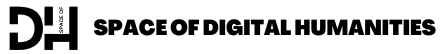



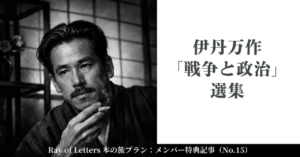



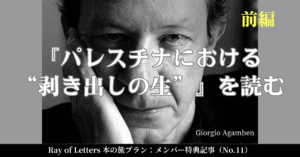
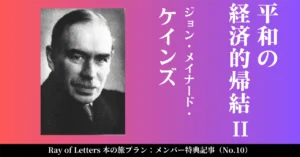
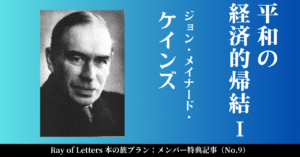

Comments