これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
タイトルにある「あの言葉」というのは、原文では「G-Word」となっています。「G言葉」と訳してもなんのことか分からないので、思い切って「あの言葉」にしました。
これは「Genocide」という単語のことですが、Gだけ言って、あとを隠すということ自体がメディアに対するケイトリンさんの痛烈な皮肉を表してるのです。
一般人の感覚では、Genocide の法的定義がなんであろうが、イスラエルのやってることは、Genocide以外のなにものでもないことが分かってきた段階になっても、大手メディアはGenocide という言葉を使うことを頑なに避けてきました。そのような目に見えにくい形で偏向報道は既に多くの研究によって暴かれています。そのような西側メディアの巧妙な偏向報道のやり方についての研究は、下の二つの記事にまとめていますので、関心のある方はご参考に。

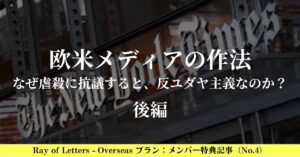
上の記事には、欧米の一流と位置付けられるテレビや新聞報道がどのような細工をして、情報の偏向を流し続けているかについて記述されているのですが、日本にそのような系統立てた研究があるのかどうか不明です。
日本では、いまだに「ハマスが人質を返せば解決する」とか、「ハマスが10月7日に攻撃したからこんなことになった」とか言ってる人が普通にあちこちにいます。もうとっくに反証されて終わった議論が日本ではいつまでも焼け跡の残火のように続いている。その火消しも行われず、世界に何十周も周回遅れの社会が出来上がってしまった。
ケイトリンさんは、しばしば西側世界の一般人に目を覚せというメッセージを込めた記事を書きますが、日本はもっと、はるかに後ろの方でもがいていることを知らないでしょう。下の記事は、ケイトリンさんのそんなメッセージが込められたものの一つです。これを読めば、日本の言論がいかにバカバカしいレベルで停滞しているかがよく分かります。

さて、今回のこの記事は、そういう偏向に満ちた報道と、それをバックアップする役割を果たしていたアカデミズムの間に、とうとう、本当にとうとうですが、変化の兆しが見えてきたことを捉えています。
この記事の元になっているのは、イスラエル人のジェノサイド専門の学者がニューヨーク・タイムズに投稿した論説です。かなり長い話ですが、それも同時に読んだ方が文脈が分かると思い、別の記事に全訳を入れました。
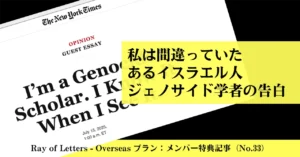
日本でも、とんでもない愚論を滔々と展開している大学教授という肩書きの人が少なからずいますが、彼ら/彼女らの主張はせいぜい数分のテレビでの主張でしか耐えられないくらい浅はかなものです。
欧米のアカデミズムのメインストリームで、ガザのジェノサイド否定論を説いているような学者の論拠は相当に精緻で、テレビのワイドショーには収まりません。そのような研究者の第一人者が、ニューヨーク・タイムズという偏向の牙城で、自分が間違っていたことを語り始めたことは一つの事件でした。
ケイトリンさんは、この記事でそれが決して孤立した事件ではなく、一つの潮流になっていることを記述していきます。それではどうぞ。

すみません、ここから先は、Caitlin's Newsletter 日本語版のメンバー専用エリアになってます。メンバーの方はログインすると読むことができます。
まだメンバーでない方は、こちらの案内をご覧ください。
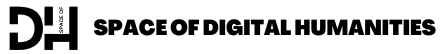

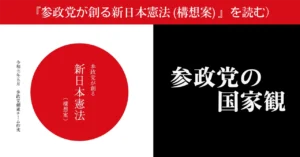
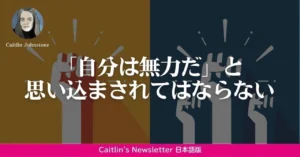

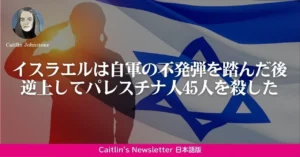





Comments