この記事は、2025年7月13日に行った、LIVE 77 『参政党憲法』を読むー参政党の国家観で話したことの骨格部分をまとめたものです。
まえがき
参政党躍進のうわさ
2025年の参議院選挙では、参政党が大躍進するだろうと複数の主流メディアが報じていた。
3、4両日に行った序盤調査では、全体の6割近くを占める内閣不支持層の投票先は参政18%、国民民主党17%、立憲民主党16%、自民党15%と分散していたが、終盤では自民が11%に減らし、立憲、国民が横ばいの一方、参政は22%に増やした。
自民の減衰や参政の伸長は、無党派層の比例区投票先の推移からも見て取れる。自民25%、立憲18%、国民12%、参政11%だった序盤から、終盤は自民が19%、立憲が15%に減り、国民は15%、参政は14%に増えた。
朝日新聞(7月14日)
比例代表の投票先は自民党が18.2%で、6月28、29両日の前回調査(17.9%)から横ばいだった。参政党は2.3ポイント伸ばして8.1%で2位に浮上し、国民民主党6.8%(6.4%)、立憲民主党6.6%(9.8%)を上回った。
テレビ朝日系「報道ステーション」が15日、放送された。参院選をめぐって、朝日新聞が行った終盤の情勢調査とANNの取材で、参政党が15議席前後の獲得となる勢いで、選挙区で7議席前後を得る可能性と伝えた。比例でも野党のトップを争っているという。
その一方で、参政党の代表兼事務局長である神谷宗幣氏の言うことがころころ変わると、SNSでは毎日指摘されていた。批判をかわすためにその場限りの反論をするからそんなことになるのか、あるいはそもそも本当に深く考え抜いた一貫性などないから、言うことがころころ変わるのか。参政党が単独なり連立なり政権に入ったら、それははっきりするだろう。
参政党は新日本憲法(構想案)というものを公開している。これについても、詳細を議論したところで、参政党は、おそらく他のすべての批判に対するのと同じ作法で、「それは”構想案”なのだから、実際に草案を詰めていく段階で変わる」というような反応をすることが予想される。実際、この構想案は、そのままでは憲法になり得ない代物なので、そういう返答自体は一応成り立つと言えるかもしれない。
詳細はまだ考え抜いていないとしても、この構想案からはっきり浮かび上がるものがある。それは参政党の持つ国家観ともいうべきものだ。他の全ての細部はそこから展開していく。
参政党が公約のように持ち出す個々のトピック(しばしばそれが公約なのかどうかはっきりしないが)に賛成か反対か考えたところで、それは前述のようにころころ変わるので、それを参政党に投票するかどうかの決定基準にするにはあまりに心許ない。
今起きている個々のトピックごとの派手な論争の裏にある参政党の持つ国家観を理解した上で、「それでも参政党を支持するのか、それなら支持しないのか」を判断するべきではないだろうか。端的に言えば、我々の国を彼らが思い描くような国にしたいかどうかということだ。
ここでは、参政党案(以下、「参政党の新日本憲法(構想案)」を「参政党案」と呼ぶ)の持つ思想の核にあると思われる特徴を3点にまとめておきたい。
I. 近代からの逸脱
憲法の設計図
憲法は「国家権力を制限する文書/契約」であり、「国民が憲法を制定する主体」である。これを否定すると、近代を否定することになり、我々(現時点での人類)の存在を否定することになる。
君主や王から一般国民が権力を奪取したことが、近代と呼ばれるものの開始であり、人類史における、その巨大な転換を反故にされないように書き記したものが憲法と呼ばれるものだ。当然、憲法を制定する主体者は国民であり、君主や王ではない。国民主権という言葉はそういう意味である。
だから、一般論として、憲法の基本設計図は、二つの柱から成る。一つは、国民に主権があるということ、その主権者のの基本的権利、つまり人権を明記する部分が、憲法にとって絶対不可欠な柱としてある。
そして、それを確実に具体的に実現するための国家の構成、つまり統治機構を明記する部分がもう一つの柱としてある。
この二つ、「人権」と「統治」が憲法の柱であり、そのような憲法によって国家を統治していくことが立憲主義と呼ばれる。
ところが、参政党案では、まず国民主権が明記されていない。つまり、柱が一本欠けている。その代わり、全面に出てくるのは「國體」や「天皇的秩序」であり、国民による国家権力に対する制限を命じる文書ではなくなっている。むしろ、参政党案は、国家から国民に対する教化的な文書となっている。
これは、憲法という文書に内在すべき指示のベクトルが逆向きになってしまっているということだ。憲法というのは、上記のように、「国民から国家へ」の指示であって、「国家から国民へ」の指示ではない。それが近代が達成した成果であったが、それを後ろ向きに過去に向かって近代を飛び越していく姿勢が参政党案に顕著に見られる。
主権について
主権という概念は、二つの方向性を持っている。
一つは、国民主権という場合の主権。この主権は、明らかに対内的な射程を想定している。つまり、ここでの主権は、「国民」が統治権力の正当性の最終的な根拠であるということを意味する。国家において、「誰が主人であるか」を言明している部分なので、憲法の最も根幹にあるものと言える。
日本国憲法では、第一条に「主権の存する日本国民」と明確に記述され、前文によってその内容はさらに明らかにされている。ところが、参政党案には、国民主権に該当する条文は存在しない。
国民主権をはっきりさせることは、憲法の出発点になるので、様々な異なる表現があっても、国民主権の主旨は各国憲法にも明記される。ただし、大日本帝国憲法のように立憲君主制の国家の憲法は、憲法という体裁があっても、主権は君主にあるので、当然国民主権に相当する条文は無い。
もう一つは、国家主権という場合の主権。この主権は、対外的な国家間関係を想定している。つまり、国家は、対外的独立性、排他性、自律性を持ち、他の国家と対等な主体として国際社会に存在することを意味する。他国に隷属したり、自律的な決定が行えない国家は、(国家)主権が欠落しているということになる。
参政党案には、主権という言葉が3回使われているが、下のように第四条と第二十一条は、明確に国家主権のことを言っている。
第二章 国家
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
参政党憲法案
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
しかし、第十九条を見ると、これは対内的な主権のことを言っているが、国家主権として記述されている。つまり、統治権力の正当性の最終的な根拠としての主権者を国民ではなく、国家としているように読むことが出来る。この参政党案の起草者がこれを明瞭に意識していたかどうかは分からないが、非常に重要なことが曖昧にされている。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる。
国民国家と国家主権
17世紀半ばに成立した「国民国家」と共に「国家主権」という概念は成長してきた。しかし、当初はヨーロッパ諸国にのみ適用され、実際これが全世界の国家に適用されるまでには300年近くかかっている。植民地の独立闘争は、その過程の最終フェーズにあると言える。
現在では、国家と言えば、独立主権国家であるというのが当然の前提であり、国際法の根幹部分である国連憲章もそれを前提にしている。第2条第7項で、他国の国内管轄事項に干渉することを禁じているのは、その前提に立っている。
従って、わざわざ「我々の国家は国家主権を持つ」と書いている憲法はほとんどない。例外的に、国家主権を憲法内で記述するものとして知られているものに、中国憲法と北朝鮮憲法がある。
興味深いことに、参政党案は、国民主権については沈黙しているが、国家主権については、上記のように三箇所で言及している。参政党案の憲法が成立すると、日本の憲法は、中国憲法と北朝鮮憲法に続き、国家主権を憲法内に規定する、三番目の憲法になるかもしれない。
国民主権と国家主権の両立
「ふつうの国家」というようなものを定式化するとしたら、国民が統治権力の正当で最終的な根拠であり(国民主権)、かつ対外的には独立した自律的な意思決定を行い、すべての国家と対等な立場を有する(国家主権)ということになるだろう。つまり、国民主権と国家主権は両立する。
対内的な意味での国民主権と、対外的な意味での国家主権を交換する必要はないのだが、なぜかどちらか一つしか選べないように考える人もいる。「日本は半独立国家だ、国家主権を確立しなければいけない」と主張し(そこまでは良いだろう)、そのために国民主権を蔑ろにする意見の人々だ。おそらくこれは、主権の意味の不十分な理解と、それによるどちらか一つを取らなければならいという単純な誤解に基づいていると思われる。
参政党案は、ほぼすべての国家が明記する「国民主権」については沈黙するが、ほとんどの国家が明記しない「国家主権」については明記するという点で、かなり変わった憲法案であると言えるだろう。
どうしてこのような風変わりな憲法案を作ったのかを解く一つの鍵は、参政党の国家観にあるだろう。彼らは、天皇を「国民を慈しみ祈る神聖な存在」とし(参政党案前文)、日本を「天皇のしらす君民一体の国家である」(参政党案第一条)と考える。「君」と「民」が一体なのだから、「民」つまり国民が主権者であることは出来ない。彼らは、「国全体が家族のように助け合って暮らす」ことを理想としている(参政党案前文)のだから、個々の「民」が個人として生きることなどは論外になる。夏目漱石が個人の自立で苦悶した時代を理想としていると言えるだろう。これも「近代の超克」の失敗の一つの形かもしれない。
II. 國體の復活
参政党案は「國體」概念を復活させる。日本の近現代史から見れば、これはかなり大きな衝撃なのだが、戦後の歴史教育の国家的失敗もしくは意図的な努力のおかげで、近現代史の知識が日本国民の頭からほぼ抹消された今となっては、素通りされる事案なのかもしれない。
まず、「国体」を旧字体を使って「國體」と表すところに、彼らの意図するところが戦前の「國體」概念にあるということが示唆されている。
國體に関しては膨大な研究の蓄積があるが、丸山眞男の論考を元に簡単にまとめると以下のようになる。
①「國體」は論理概念ではなく観念形態である
「國體」は近代的な論理的概念ではなく、曖昧で情緒的な観念形態(イデオロギー)である。定義があいまいであるがゆえに、批判や検証の対象になりにくく、信仰の対象として機能した。
②政治的道具としての「國體」
國體論は、国家の統治権力を正当化するイデオロギーとして利用された。特に、天皇制の神聖化と結びつけられ、「萬世一系」「天壌無窮」などの神話的表現が政治権力の根拠とされた。
③「無責任の体系」としての國體イデオロギー
國體論のもとでは、権力の所在が不明確となり、統治の責任も曖昧になる。たとえば、戦争責任を天皇に帰すことはできず、同時に政府や軍部も責任を明確に負わないという、「無責任体制」が形成された。
④國體と近代合理主義との乖離
國體論は、合理主義・法治主義・民主主義と本質的に相容れない。形式的には近代憲法を持っていても、その根底には超歴史的・宗教的権威としての天皇観が支配しており、「近代的立憲主義国家」とは異質なものだった。
⑤ 「國體の喪失は亡国である」という教義
國體は「絶対不変」であり、それを改変しようとする行為は「国を滅ぼす」行為と見なされた。この論理により、あらゆる改革的・自由主義的思考が「国賊」として排除された。
1945年7月26日に発せられたポツダム宣言の受諾を最後まで阻んだのがこの「國體の護持」、つまり「天皇制存続」の祈願であった。戦争に負けたのは誰もが分かっていた。しかし、「國體の護持」だけは死守しようと強硬に主張する者たちを説得できないまま時間は過ぎていった。彼らにとって、國體の喪失は亡国であったのだ。そして、原爆が二発落とされた。
日本政府は8月9日になって、「國體の護持」は許されるかと連合国に問い合わせをしたが、連合国の回答は、「天皇の地位は日本国民の自由な意思によって決定される」というものだった。ポツダム宣言の受諾は、国民主権に基づく民主的な国家を作ることへの同意であったのだから、当然「國體の護持」などはあり得ないのだが、当時の日本政府は、これは「國體の護持」が許されたと都合よく誤解した。
余談になるが、その都合の良い誤解は、憲法草案作成過程に大きく影響し、今から振り返れば、まるで笑い話だが、日本政府は國體を護持したままの草案を作ってしまった。当然、これはポツダム宣言を受諾した以上、約束に違反したことになる。「押しつけ憲法論」の誤謬はここにある。
日本国憲法は、草案を誰が作ろうが、ポツダム宣言を受諾した以上、その趣旨を反映したものでしかあり得なかった。強いて「押し付けられた」という言葉を使えば、「押し付けられた」ものはポツダム宣言だったとは言えるかもしれない。しかし、戦争をして決着をつけようとして、そして、日本は負けた。勝者が敗者に終戦の条件を”押し付けた”と言ったとして、それは戦争である以上、最初から分かっていることだ。戦争をするというのはそういうことも含まれる。しかし、押し付けてもらわなかったら、もっど酷いことになっただろう。
参政党案には、「國體」という言葉が以下のように2回出てくる。
前文
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあるべき道を示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。 これが今も続く日本の國體である。
参政党憲法案
第五章 統治組織
(統治原理)
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
参政党憲法案
これらの条文に、國體こそが国民の上位にある優越した価値であるという思想を読み取ることは難しく無いだろう。まるで戦前のように。
③通俗道徳の混入
権利と義務・自由と責任
参政党案は、「権利と義務」及び「自由と責任」について以下のように規定している。
第八条 3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない(18)。
注(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉 (公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に 限られ、濫用を禁止する趣旨である。
参政党憲法案
なお、参政党案は、権利に「権理」という字を当てている。その理由として、以下のような注が付いている。
(13) 権利を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた。
参政党憲法案
「権利には義務が伴い、自由には責任が伴う」というのは通俗道徳ではよく聞く言葉であるだろう。しかし、憲法は道徳文書ではない。この通俗道徳がそのまま憲法の理解に使えると考えるのは大きな誤解である。
憲法上の権利とは、何かと引き換えにもらえるものではない。憲法上の権利は、何かの対価ではない。生まれながらにして全ての人間がもつ自然権としての基本的権利が憲法上の権利なのだ。だから、それは無条件で一方通行的なものでなければいけない。
こういうことを言っても、承服できない人が多くいることは、経験的に知っている。しかし、少し立ち止まって考えて欲しい。仮にあなたがこのような考え方が成立するよりもずっと前に生まれていたとしよう。あなたは勤勉でよく働き、武運にも秀でてあなたの国のお殿様にとても気に入られたとしよう。そのおかげで、あなたはお殿様に他の平民が持たない自由と権利を与えられた。
この関係はあなたとお殿様の間の取引に過ぎない。お殿様はあなたの自由も権利もいつでも奪えるのだから、それはそもそも自由でも権利でもなんでもない。お殿様に一所懸命「奉公」し、有り難く与えていただく「御恩」という関係は単なる封建制度と呼ばれるもので、自由も権利も何の関係もない。それが日本の通俗道徳として人々の間に深く根付き、自由も権利も言葉だけが流通して、いまだに我々の社会は近代的な意味での自由と権利を獲得していないと言える。
もし、責任や義務が自由や権利の前提条件であると、どのような国家が出来上がるだろうか?それは、国民の自由や権利が国家の定めた倫理的基準に従属するような国家になるだろう。人類は実際にそのような経験をしてきたので例を見た方が早い。
ワイマール憲法は、個人の自由や社会権が明確に盛り込まれた当時の水準で最も民主的な憲法であった。しかし、ナチスは、「自由は共同体に奉仕する限りにおいて尊重される」とか、「権利はドイツ国民としての義務を果たして初めて認められる」というナラティブを使って、巧みに国民の自由や権利を剥奪していった。その結果どうなったか?
大日本帝国憲法にも、天皇主権のもとだが、臣民の権利は規定されていた。ただし、すべて「法律の範囲内で」のみ保障された。そして、『教育勅語』や『修身』の教科書によって、国民は、「自由は放縦に非ず」とか「権利は義務を尽くしてこそ得られる」という個人の自由は常に家族や国家への忠誠に従属するという道徳を教えられた。その結果どうなったか?
興味深いことに、参政党案は、教育に関して、こんなことを規定している。
第九条 3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
「修身」を必修にしたいそうだ。「修身」とは、上で若干触れたように、明治時代(1879年/明治12年)に採用)から、1945年の敗戦まで日本の教育課程で用いられた道徳教育科目の名称であり、儒教的価値観をもとに、家庭・社会・国家における個人の徳目(忠孝・礼儀・勤勉など)を教えるものだった。
しかし、「修身」は単なる「徳目の体系としての行動規範」にとどまらず、「国家の価値体系に従順な臣民を育成するための教化装置」となり、大惨事の基盤になったことは歴史に証明された。だからこそ、このような通俗道徳の国家規範化の弊害は語り継がなければいけないことの一つなのだが、日本の教育課程からはきれいさっぱり抹消されたようだ。
「公共の福祉」と「公益」
参政党案に紛れこんだ通俗道徳の例をもう一つ挙げる。
「公共の福祉」という言葉は、日本国憲法で使われる用語で、全部で3回出てくる。「公益」という言葉は、参政党案で使われる用語で、全部で14回出てくる。
非常によく似たイメージの言葉で、日常の会話ではどっちも同じように使われても、まず支障はないだろう。ところが、これが憲法上の用語となると、天と地がひっくりかえるくらいのまったく異なる意味になる。
日本国憲法における「公共の福祉」は「権利の限界原理」と呼ばれるものです。ある人の権利と別のある人の権利が衝突した場合、それを調整しなければいけない。その時の調整メカニズムのことを「公共の福祉」と呼ぶ。具体的には裁判所が調整するということになる。
日常の言語感覚から言えば、非常に分かりにくいと思う。すんなり腑に落ちない場合は、いったん頭の片隅に休憩させておいて、後で考え直すのもよいと思います。
それでは、参政党案の「公益」は、なんなのか?これは、国家が望ましいと考える価値を定め(例えば、家族や道徳や國體など)、それを「公益」と呼び、権利の行使を制限するという論理です。
ここで非常に重要な点は、日本国憲法における「公共の福祉」は、「人権は人権によってのみ制限される」ことを徹底するための原理であるのに対し、参政党案(自民党改正草案も同様の考え方です)における「公益」は、人権に優越する価値を国家が定めて人権を制限するということです。
ここで前節を思い出してほしいのですが、「公益」理論における権利はもはや権利でさえないのです。取引材料に過ぎません。繰り返しますが、「公共の福祉」とは、権利の調整手段のことであり、「公益」とは、権利の前提・上位価値のことです。
ややこしい話かもしれませんが、寝言を言ってるわけではありません。「公共の福祉」論は、最高裁判決によって確立しています。興味のある方は、薬事法判決(最大判1975)を調べてみてください。
世の中には様々な道徳規範があり、いかなる道徳を選ぶかは個人が判断するのが近代国家の原則だが、参政党案に表れているのは、国家を家父長制的にとらえ、親である国家が道徳を決定し、子である国民にそれを教化するという姿勢だ。そこから悲劇が始まることを、既に人類は経験しているにもかかわらず。
結論
以上、参政党の新日本憲法(構想案)というものをマクロ的視点から見て、①近代から逸脱し、②國體を復活させ、③通俗道徳を混入させるという3点にまとめてみました。本来は憲法学者が逐条的に解釈して論評するべきでしょうが、おそらく誰もしないと思います。標準的な学識のある憲法学者なら時間の無駄と判断されると思うからです。
最後に個人的な感想ですが、この人類の歩みをごっそり踏み外したようなものを堂々と公表できる度胸には敬意を表しますが、内容が時代錯誤に過ぎて、これを本気で憲法に出来ると思ってるのか疑いが残りました。但し、これを参政党のマーケティング文書と見ると、日の丸をモチーフとした表紙、神話的な装い、復古調のレトリック、やまとことば的言葉遣い、あるいは明治期的な造語など、ターゲット層には訴求力のある、かなり優れたプロダクトかもしれません。
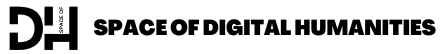
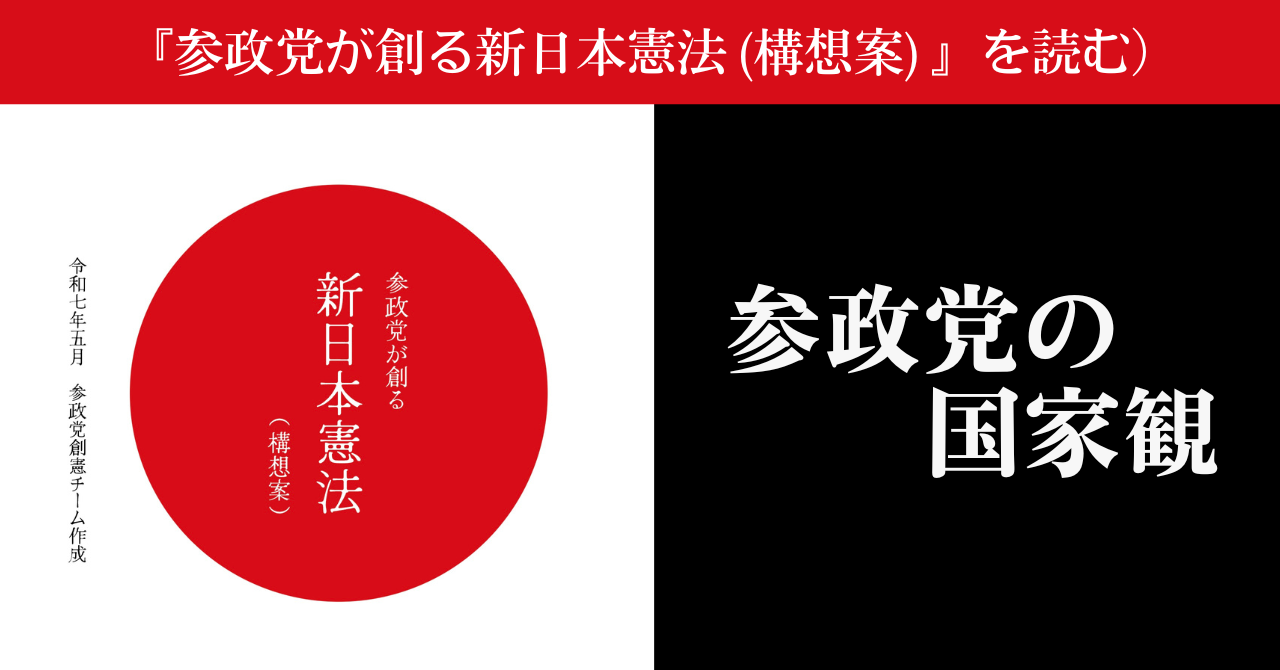



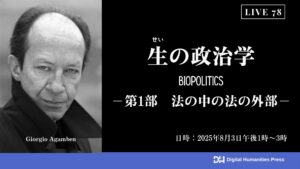


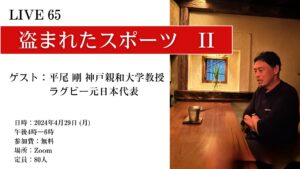
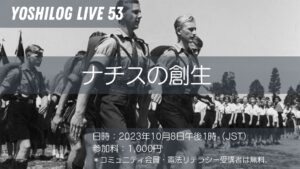

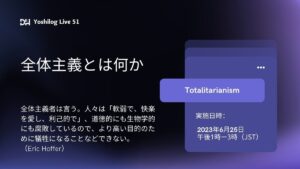
Comments