これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
[無料版]
X上で下の投稿について返信したので、少しだけ加筆修正してここに載せる。
@yoshilog 参考までに、UNOHCHRのNY事務所元所長のクレイグ・マカイバー氏はこんなことを訴え続けています。ただ、これからのアクションを各国が起こすには、世界中の市民社会からの圧力が必要だと。そうでないと「政治的意思」が十分生じないと言います。どう思いますか?https://t.co/2QEJZBZwrm— 💫T.Katsumi@X 🌍🌏🌎 (@tkatsumi06j) September 14, 2025
上記投稿に引用されているCraig Mokhiber氏の投稿の訳は以下の通り。
上記X投稿訳:
Craig Mokhiber @CraigMokhiber
緊急: 今週は、国連総会(UNGA)がパレスチナでのジェノサイドを止めるために実際の行動を取れるかどうかを決する、正念場の週となる。だが、それを妨げようとする強力な勢力が動いている。
国連総会は、イスラエルの資格を拒否し、制裁と武器禁輸を要求し、反アパルトヘイトの仕組みを再活性化し、刑事法廷を設立し、さらに保護部隊に民間人を守り、人道支援を確保し、イスラエルの犯罪の証拠を保存し、復興を開始することを委任することができる。
これを実現するために、http://LifeLineForPalestine.Com, http://stopgenocide.com, http://u4pal.com, http://peopleagainstgenocideeverywhere.org にアクセスしてください。
この投稿で、クレイグ・マカイバー氏は国連総会が出来ることとして8つ列挙しています。
1. イスラエルの資格を拒否し、
2. 制裁と軍事禁輸を求め、
3. 反アパルトヘイト機構を再活性化し、
4. 刑事裁判所の設置を決定し、
5. 民間人保護のための保護部隊を派遣し、
6. 人道支援を確保し、
7. イスラエルの犯罪の証拠を保全し、
8. 復興を開始することができる。
彼は国連の制度をよく知っているので、その限界の中で出来ることを熟考した上で書かれています。これらは全て制度上可能であり、先例のあるものです。
「1. イスラエルの資格を拒否」という悩ましい言葉使いをしているのは、現実性を考慮しているからでしょう。
加盟国の除名のためには、まず安保理が決議する必要があるので、この場合、アメリカが拒否権を発動して反対するので、総会での審議にまで辿り着かないでしょう。(国連憲章 第6条)
国連憲章 (除名)
Article 6
A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.
第6条
国際連合の加盟国であって、本憲章に掲げる原則を繰り返し違反したものは、総会において安全保障理事会の勧告に基づき、国際連合から除名することができる。
資格の停止についても(第5条)、まず安保理の決議が必要で、その後総会の3分の2決議で決定されるので、除名と同じく実現性がありません。
国連憲章 (資格停止)
Article 5
A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.
第5条
安全保障理事会が予防的措置又は強制措置をとった国際連合の加盟国は、総会において安全保障理事会の勧告に基づき、加盟国としての権利及び特権の行使を停止されることができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会により回復することができる。
しかし、これまで加盟国を”追い出した”先例はあります。1971年、台湾(中華民国)は、国連総会決議2758により国連への中国の「代表権」を失い、中華人民共和国が中国を代表することになりました。つまり、台湾は安保理の決議なしに総会決議のみで国連から実質的に追い出されたのです。法技術的な建前は、これは「代表権問題」であるとしながら、実態としては「除名」したのと同じことです。マカイバー氏が何を念頭においてるのか分かりませんが、この辺りのことは熟知しているでしょう。
「2. 制裁と軍事禁輸」や、「5. 民間人保護のための保護部隊を派遣」に関しては、軍事(強制措置)が伴うのだから、安保理決議が必要だと普通は考えますが、彼が下の投稿でも書いているように、「緊急特別総会 (Emergency Special Session, ESS)」を想定していると思います。別名「平和のための結集」決議です。
The UNGA voted overwhelmingly today to “endorse” the New York Declaration put forward by France & Saudi Arabia. Among its many problematic provisions, the Declaration supports a “stabilization force” (with many bad elements as well), instead of a protection force as such. But the…— Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) September 12, 2025
上記X投稿訳:
Craig Mokhiber @CraigMokhiber
今日、国連総会(UNGA)は、フランスとサウジアラビアが提起した「ニューヨーク宣言」を「承認(endorse)」することを圧倒的多数で採択した。多くの問題含みの条項の中で、この宣言は、本来の保護部隊(protection force)ではなく、「安定化部隊(stabilization force)」(多くの悪しき要素も伴う)を支持している。
だが、今日採択された決議は、安定化部隊を義務づけるものではない。それは単に、安全保障理事会において提案されるよう求めただけであり、そこでは米国が確実に拒否権を行使するだろう。
したがって、昨年の国連総会の一年期限に関連して「さらなる措置」を採択するために、「平和のための結集(Uniting for Peace)」に基づく国連総会緊急特別会期への働きかけが続けられている。
その「さらなる措置」には、制裁、軍事禁輸、イスラエルの資格停止、法廷(tribunal)、反アパルトヘイトの仕組み、そして保護部隊が、なお含まれ得る。これは険しい道のりだ。しかし、ジェノサイドが猛威を振るう中で、全ての代表団に対し、公然の注視のもと(タートルベイの陰でではなく)、保護(正常化ではなく)の呼びかけに「イエス」か「ノー」かを表明させよう。
訳註:
1. stabilization force(安定化部隊):国連や地域機構が紛争後の状況に派遣する「治安安定化部隊」を指す。
典型的には、軍事的存在を長期間にわたって維持し、既存の秩序や停戦ラインを固定化することを目的とする。
批判される点:
占領状態や既成事実を「固定化」してしまい、根本的な問題解決を妨げる可能性。
外国軍の駐留を恒常化する道具になる恐れ。
2. protection force(保護部隊):国連や国際社会が 民間人の保護 を主目的に編成する部隊。
具体的には、ジェノサイドや民族浄化の危険にさらされている住民を守るための即時的・緊急的な展開を想定。
「安定化部隊」と異なり、秩序の維持ではなく人命の保護が第一目的。
3. Turtle Bay(タートルベイ):ニューヨーク市マンハッタン東側の地名。国連本部ビルが建っている地域として有名。
「the shadows of Turtle Bay(タートルベイの陰で)」とは、国連本部の裏で行われる密室外交や不透明な交渉を暗示する比喩。
Mokhiberはこれに対して、「glare of publicity(公然の注視のもと)」=公開性と透明性の中で各国の態度を明らかにせよと対比させている。
アイルランドのマイケル・D・ヒギンズ大統領も同様のことを言っていたことが報道されている。
Irish president calls for a UN military intervention in Gaza
ESSの根拠は、国連憲章にはなく、1950年の総会決議377 A (V)「平和のための結集(Uniting for Peace)」にあります。これは「安保理が大国(常任理事国)の拒否権行使によって機能不全に陥った場合、総会が「国際平和と安全の維持」に必要な勧告を緊急特別総会で行えるようにする」というものです。
この時は、朝鮮戦争の時で、米ソ対立で安保理がにっちもさっちも行かなくなっていました。その後も、ESSは、1956年のスエズ危機(第1回緊急特別総会)、1981年のナミビア問題、1997年以降の「パレスチナ問題に関する第10回緊急特別総会(ESS10 )」などで使われました。現在もESS10は休会中扱いでなので、再開可能です。
ESS決議で、国連総会は加盟国に対し「軍事行動への参加」を強制する拘束力はありませんが、「呼びかける」ことは可能になります。参加したい国の自発的意思で参加すれば良いのです。これは、欧米が勝手によく作る「有志軍/連合」とは違って、国連総会に公的にお墨付きを得た「有志軍/連合」になります。
ESSベースの「有志連合による武力行使」の費用は国別負担になりますが、ESSベースの「非強制的活動(平和維持)」の費用は、国連経費でカバーすることが可能です。これに関しては、1962年にICJが認めました。
ESSベースの朝鮮戦争では、国連軍(といっても実質はほぼ米軍)の費用は国別負担になりましたが、UNEF(1956スエズ危機)やONUC(1960コンゴ危機)は安保理に基づかない総会ルートの平和維持活動で、国連の費用負担になりました。常設の国連軍は存在せず、国連軍と呼ばれているものは成立根拠も活動内容も全て異なるのですが、もちろん日本ではメディアどころか、最近は政治家/学者もごちゃまぜにしているので話がワカメになります。
「3. 反アパルトヘイト機構を再活性化」は、南アフリカがアパルトヘイトを維持していた時に様々な機構が作られましたが、イスラエルのアパルトヘイトに活用しようということでしょう。
例えば、国連反アパルトヘイト特別委員会、国連反アパルトヘイト国際センター、1973年「アパルトヘイト犯罪防止および処罰に関する国際条約(Apartheid Convention)」を起草し、法的にアパルトヘイトを国際犯罪としたことなど。
「4. 刑事裁判所の設置」は、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)や、ルワンダ国際刑事裁判所(ICTR)などは有名なので、これらを思い出すと思いますが、この二つは安保理の勧告があって成立したものなので、アメリカが安保理にいる限り同様の形式では出来ないでしょう。但し、安保理の関与無しか、ほぼ無い刑事裁判所も過去には設置されたことがあります。例えば、カンボジア特別法廷(ECCC, クメール・ルージュ裁判)は総会の決議だけで成立したものなので、イスラエルに関しても同様の刑事裁判所を設置する可能性はあると考えたのでしょう。
「6. 人道支援を確保」、「7. イスラエルの犯罪の証拠を保全」、「8. 復興を開始」などは、安保理の決議は必要要りません。むしろ単独の国家単位でも始められることです。
最後に二国家解決案と国家承認についてですが、二国家解決案は、現実の問題を何一つ解決しません。むしろそれはオスロ合意以来、50年間民族浄化の根拠に使われてきたのです。日本の政治家にも、パレスチナの国家承認をすれば、ジェノサイドと民族浄化を止めることが出来るかのようなことを言ってる人がいますが、非常に悪質です。
その点、マカイバー氏は、どうしたらイスラエルの悪逆非道な反文明的な蛮行を止めさせるかを具体的に現実的に考え尽くしているように見えました。長いのでとりあえずここでやめますが、ここに書いたことはすべて公式の外交として行えることです。しかし、現実にはこれらはすべて時間がかかり、実効性も保証されません。そこで、今まではグリコのオマケのように見なされていた民間の出来ることに注目する人が出てきています。これについては別稿にします。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
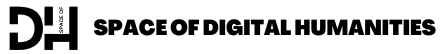
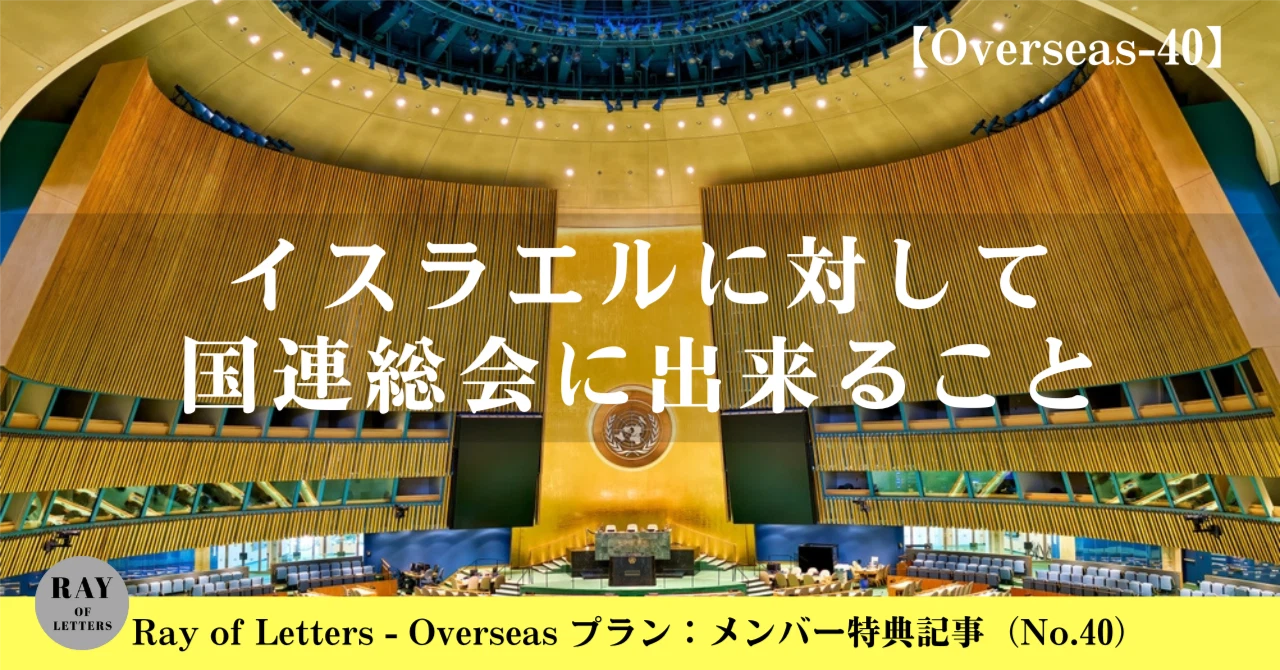

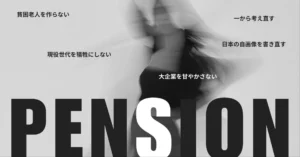
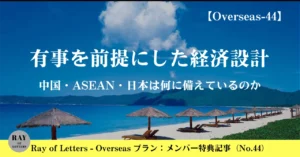
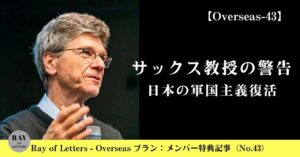
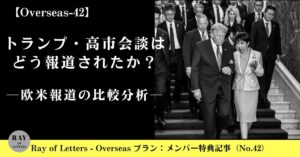
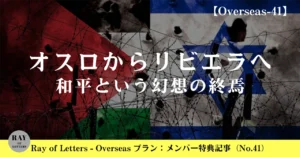


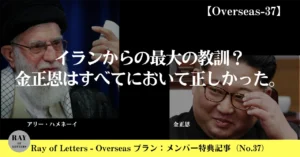
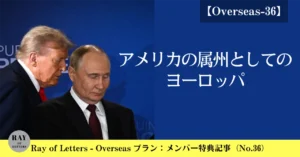
Comments