これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
上のカバー写真は、2023年5月、ヴォトキンスク(Votkinsk)を訪れるスコット・リッターです。
目次
- ロシア再訪
- 2024年−言論の自由を剥奪
- 2025年−パスポートの回復
- National Unity Club
- 1994年−無知の罪
- Citizen Diplomacy/市民外交
今年8月ちょうどアラスカでプーチン大統領とトランプ大統領が会っていた頃、偶然のタイミングですが、スコット・リッター氏はロシアを訪れていました。
リッター氏は、今回のロシア訪問についていくつかの記事を書き、YouTube でも話しています。その一つが、ロシア滞在中に配信された Return to Russia(2025年8月10日)という記事です。
この記事の中で、ロシアへ何しに行ったのかということが説明されています。まず、去年2024年6月にリッター氏が、ロシアのサンクトペテルブルク国際経済フォーラムで講演をするために、ニューヨークのJFK空港へ行った時に、パスポートを没収されたところから話が始まります。その2か月後、数十人の武装したFBI捜査官がリッター氏の自宅に押し寄せ、彼の個人用コンピュータなどを押収していきました。どちらのケースも罪状は知らされずに。
リッター氏は、言論の自由を非常に重要視しています。彼はこれまでもものごとをはっきり言う人として有名であり、アメリカ政府に常に目をつけられていました。この辺は、【Overseas-27】ウクライナ:崩壊か核戦争かを読んでいただくとより明瞭になると思います。
彼をトランプ派だとか、その逆に反トランプ派になったとか思ってる人もいるようですが、それはどちらも誤解です。彼の話をよく聞いていると分かるはずですが、リッター氏は党派性から最も遠いリアリストです。その点では、極端なリアリストであるシカゴ大学のジョン・ミアシャイマー教授と同じです。
リッター氏やミアシャイマー教授は、トランプの言うこと、やることを厳しく批判することもあれば、支持することもあります(もっとも最近はほとんど批判ですが、それはトランプの問題です)。つまり、彼らは、「あの人間だから」とか、「あの組織だから」とかいう理由で、全部賛成/全部反対というのではなく、個々の事象(言ったこと、やったこと)について分析し、評価するという姿勢を維持している人たちです。
さて、トランプ政権になり、彼はパスポートを再取得し、ロシアに行けることになりました。
そこから、話は1994年に遡ります。冷戦直後のアメリカが浮かれていた頃です。”貧乏でかわいそうな”ロシアを助けてあげようという態度でアメリカはロシアにアプローチするのですが、ここでリッター氏は、アメリカ人のロシアに対する無知がいかにアメリカの政策を誤らせたかを説明します。
その中で「援助観光客」という言葉が出てきますが、これは個人的にはまざまざと目に浮かんできました。職業的に15年間アフガニスタンやイラクのフィールドにいましたが、まさに「援助観光客」という現象がそこにはあります。ひとたび戦闘が終わると、全世界から「助けてやるのだ」という高揚感にあふれた人たちが集まってきます。
しかし、大問題は、彼らは現地について何も知らないのです。歴史も地理も文化も言語も習慣も何も知らない。ましてや、現地の微妙な政治状況など理解できるわけもない。自分が思い描く「援助」が、現地の必要とまったくミスマッチであるということには全く関心がない。彼らにとって大事なのは、「自分は助けてやった」と思うことなのです。
例えば、敵対する勢力がかろうじて均衡を保っている時に、その一方を武装解除して、虐殺、強姦、略奪のあらしを起こし、それが大量の避難民を生み出してしまうなんていうバカげたことも実際に起きるのです。
ところが、「援助観光客」はなんの反省もなく、それを手柄話として吹聴して生きていきます。まるで一国の不幸は、一旗あげるチャンスとでも考えているようです。それを「援助観光客」と呼ばれてもしょうがないでしょう。
ロシアで巻き起こったアメリカ人の援助観光は、非常に深刻な結果を引き起こしました。それは「ロシア嫌悪(Russophobia)」を増幅し、アメリカ政府はそれを利用してきたのです。
政府、学界、メディア、ハリウッドなど全てを含むアメリカ社会を蝕む「嫌露(Russophobia)」は、アメリカ市民にとってロシアの現実を自ら読み解くことをほとんど不可能にしているとリッター氏はいいます。冷戦後の無知なアメリカ人のロシアとの関わり方が「嫌露(Russophobia)」をここまで増幅させてしまったのです。
これは日本人にとっても他人事ではないでしょう。日本に蔓延する「嫌中(Sinophobia)」者たちは、もはや中国の現実を読み解くどころか、理解できない状態になっている。彼らの言ってることが表しているのは、アメリカ人のロシアに関する無知が「嫌露(Russophobia)」を増幅させたように、日本人の中国に関する無知が「嫌中(Sinophobia)」の土壌になっているということです。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
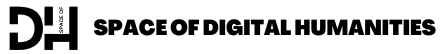


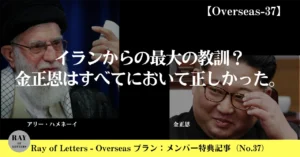

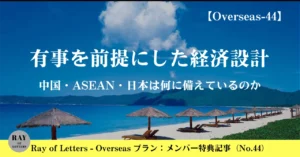
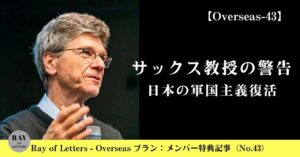
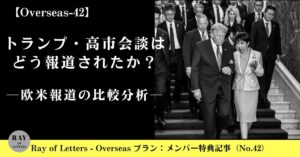
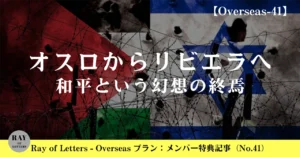
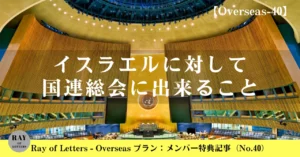
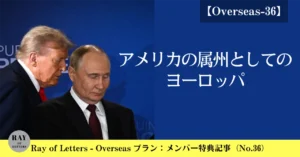
Comments