これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
[19,848字]
ジョン・メイナード・ケインズ『平和の経済的帰結』- Iとほぼ同時に書いたのですが、なんどか書き直しているうちに発信が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
本書は構成がしっかりした本です。それを崩さないように、現代の読者が受け取るべきことを見失わないように注意しながら要約していきました。
難しそうに見えるかもしれませんが、経済についてまったく知らない人でも非常に読みやすく、しかも外交の現場が生き生きと描かれており面白い本です。
ケインズの目を借りて、この書の中に入り込むと、理想と現実という言葉を使えば、陳腐な表現になってしまいますが、人間がいかに理想を追求して、現実に敗退し、また理想を語る営みに触れ、胸が熱くなるかもしれません。そんな書です。
目次
- ケインズの『平和の経済的帰結』
- 本書の成立と目的
- 第一章 序論
- 第二章 ヨーロッパの経済的背景
- 1. 人口
- 2. 社会的まとまり
- 3. 社会心理
- 4. 旧世界と新世界の関係
- 戦前の「経済的黄金時代」
- 経済的相互依存の深まり
- 戦争による構造の破壊
- 食糧と資源の混乱
- 道徳と制度の空洞化
- 第三章 会議
- パリ講和会議の舞台裏
- ロイド・ジョージ:機敏だが原則に欠ける現実主義者
- クレマンソー:復讐心に駆られた強硬派
- ウィルソン:理想主義に溺れた無力な理想家
- 指導者たちの失敗が招いた不安定な平和
- 第四章 条約
- I. 海外商業
- II. 石炭と鉄鋼
- III. 輸送と関税制度
- 戦争責任条項
- 第五章 賠償
- I. 和平交渉に先立つ約束
- II. 会議と条約の条件
- III. ドイツの支払能力
- IV. 賠償委員会
- V. ドイツの逆提案
- ドイツの戦後状況:疲弊と混乱
- 食糧不足と都市部の飢餓
- 財政の危機とインフレの兆候
- 生産能力の分析:潜在力はあるが活用不能
- 過剰な負担は「破壊」に直結する
- 第六章 条約後のヨーロッパ
- 経済復興策の欠如
- 戦勝国間の経済的連携の欠如
- 新興国家の不安定性とロシアの孤立
- ヨーロッパ経済の崩壊と社会的混乱
- 経済的相互依存の重要性と将来への警鐘
- 第七章 修正案
- I. 賠償金の削減と現実的な支払い計画
- II. 戦債の相互放棄と国際的な金融協力
- III. 食料と原材料の供給支援
- IV. ヨーロッパ経済の統合と協力体制の構築
- V. ロシアとの経済的関係の再構築
- VI. 国際的な経済機関の設立
- 提言1:賠償制度の抜本的見直し
- 提言2:食糧と必需品の国際的供給
- 提言3:国際金融制度の再建
- 提言4:国際貿易の自由化と障壁撤廃
- 提言5:新たな国際協力体制の構築
- 平和の経済的前提とは何か
- 本書から学ぶべきもの
- 平和条約はなぜ誤ったのか
- 戦争は終わっていない
- ケインズの予見の的中
- 経済の果たすべき役割
- 本書の現代的意義
ケインズの『平和の経済的帰結』
本書の成立と目的
この書は、ケインズの失望と怒り、そしてそこから生まれた提言の書です。第一次世界大戦後、ケインズはイギリス財務省を代表してパリ講和会議に参加していましたが、そこで目撃した講和交渉の実態に彼は深い失望を覚えます。
会議は、平和の理想やヨーロッパ復興という大義とは裏腹に、狭量で復讐的な動機に基づいて進められており、その条約内容が経済的に持続不可能であり、平和をもたらすどころか次なる混乱と戦争の原因になると、ケインズは会議中に確信するに至りました。
その結果、彼は会議途中で抗議の辞任をし、イギリスに帰り、彼が目撃した会議の実態と自らの見解を2ヶ月で一気に記録したのが本書『平和の経済的帰結(The Economic Consequences of the Peace)』です。
この著作は、単なるパリ会議の批判にとどまらず、指導者の人物像、戦前の経済秩序、賠償問題、ドイツの経済状況、そして復興のための提案までを総合的に論じています。
彼は、経済学者の立場から冷徹な分析を行うとともに、人道的な視点も貫いており、本書は経済書であると同時に、道徳的かつ政治的警告としての性格も持っています。
本書は以下のような構成になっています。
第一章 序論
第二章 戦争前のヨーロッパ
第三章 会議
第四章 条約
第五章 賠償
第六章 条約後のヨーロッパ
第七章 修正案
第一章 序論
序論ではまず、戦争が終わった当初、ヨーロッパの人々の間に希望があったことが述べられます。とくに、アメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソンが提唱した『十四か条』は、多くの人々にとって、公正で、今の言葉で言うと持続可能な国際秩序が築かれるという期待を抱かせました。ケインズ自身もまた、ウィルソンの理想主義に共感を覚えた人物の一人でした。
しかし、実際の講和会議ではその期待が裏切られました。会議は公開の場ではなく、少数の政治家による密室協議によって、主に英米仏伊の4カ国に支配され、道義的理想よりも報復や国内政治の思惑が優先されました。
とくにフランス首相クレマンソーとイギリス首相ロイド・ジョージは、ドイツへの懲罰を強く主張し、経済的・地政学的な制裁を徹底しようとしました。現実的交渉力に欠けるウィルソンは彼の理想が言葉尻だけになるのを止められず、結果として講和条約は極めて厳しい条件をドイツに課すこととなりました。
ケインズは、こうした講和のやり方がヨーロッパの復興にとって有害であるだけでなく、将来的な不安定化を招く危険性をはらんでいると警告します。とくに彼が強調するのは、会議参加者たちの経済的側面の無理解です。政治指導者たちは、復興の前提となる経済循環や貿易の回復よりも、制裁や賠償に熱中し、ドイツ経済を締め上げることが自国の利益になると誤認しているとケインズは言います。
序論の終わりでは、本書の目的が明確にされます。すなわち、ケインズは単なる政策批判にとどまらず、この誤った講和がいかにしてヨーロッパの経済的崩壊と将来の戦争を引き起こすかを論証することにあると。
彼は経済学者としての専門知識と現場の観察に基づき、現実的かつ警鐘的な分析を本書で試みます。理想を裏切られた知識人としての怒りと、経済合理性に基づく警告とが融合した文章であり、本書全体のトーンを象徴する章です。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
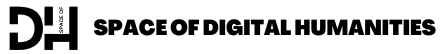
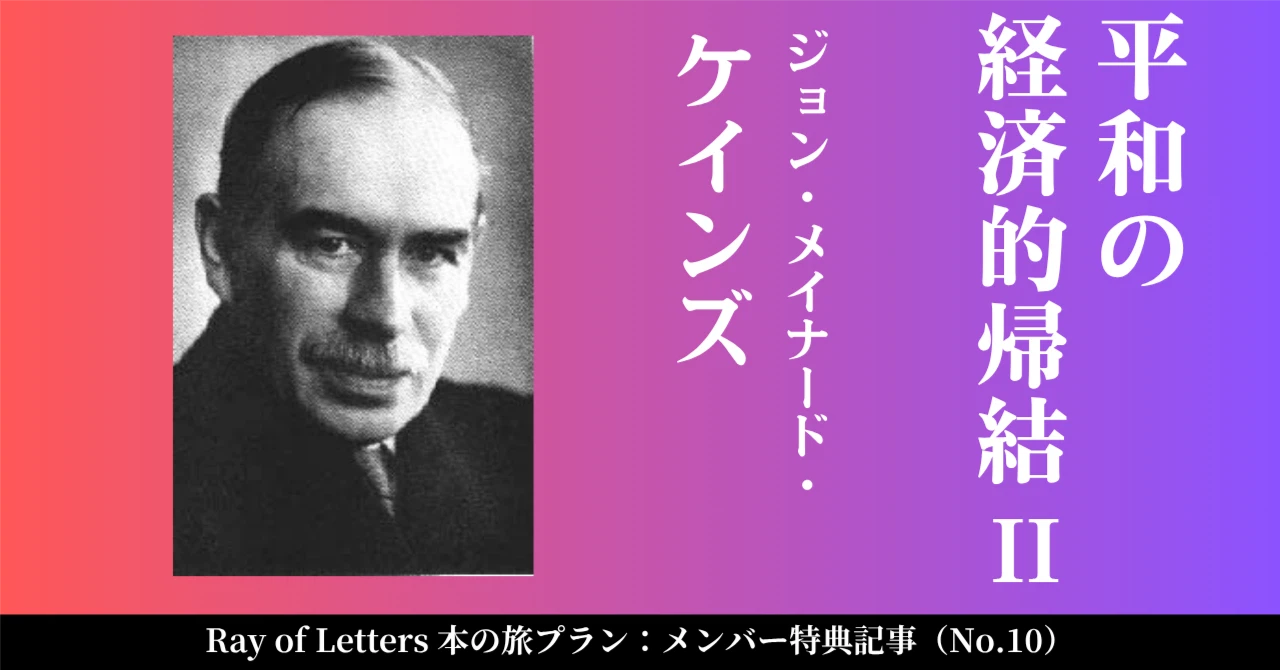

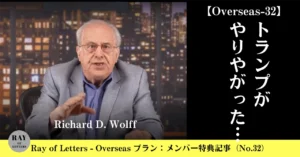

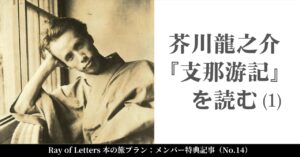
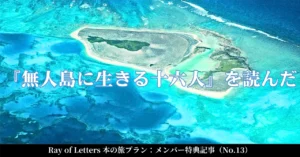
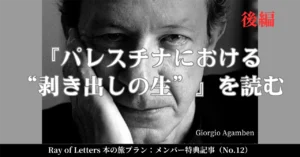
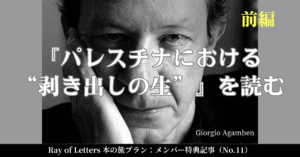
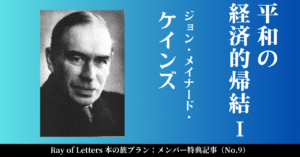

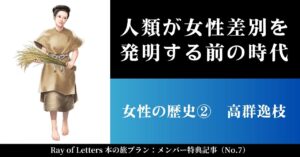

Comments