これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
今回のケイトリン・ジョンストンさんによる記事は、2025年6月16日に配信されたものなので、日付的には若干遡るが、どこの国の人でも、もし自国を巻き込む戦争が現実のものとなれば、誰もが考えるべき、あるいは考えざるをえないことについて、彼女は触れているので、ちょっと後戻りして取り上げることにした。
とても短い記事だが、とても強い印象が残った。
戦争の理由が、正義のためであろうと、自国政府の大失策のせいであろうと、理不尽に攻撃してくる他国のせいであろうと、そんなこととはまったく関係なく、皆が決断を迫られることの一つは、一人の個人として自分も殺し合いに参加するのかどうかということだ。
裏切り者、非国民、腰抜けと罵られても殺し合いを忌避するという立場もあるだろう。思想的に、なんらかの信条として、あるいは宗教的に殺し合いがどんなに嫌でも、日本を愛するがために、お国のために戦うという立場もあるだろう。あるいは、不当な攻撃をしかけてきた憎っき敵を懲らしめるのが正義だと信じて人殺しに向かうという立場もあるだろう。
武器や兵器がどうしたこうした、国際法がどうしたこうした、戦略がどうしたこうしたという話は、実際に戦争になれば、国民ほとんど全員にとって、まったくコントロールできない問題になる。しかし、極めて私的で、個人的で、下世話なレベルで、自分は殺し合いに参加するかどうかという問いが残る。
誰も殺し合いに来ない戦争なんてものがあったら、その戦争はどうなるだろう?
この記事のタイトルは「Let It Be The War That Nobody Comes To」というものだ。直訳すると、「もしイランとの戦争になるなら、それは誰も来ない戦争であってほしい」みたいになる。つまり、ケイトリンさんは「誰も来ない戦争(The war that nobody comes to)」になってしまえと言っているのだ。
ケイトリンさんは、この記事の中でカール・サンドバーグ(Carl Sandburg)の詩を引用している。サンドバーグは、日本ではあまり知られていないが、1878年から1967年まで生きた、アメリカでは有名な詩人であり、作家であり、ジャーナリストでもあった。リンカーンの伝記を書いた人として知られている。『The War Years』という作品でピューリッツァー賞(歴史部門)を受賞した人でもあった。
ケイトリンさんが引用したサンドバーグの詩の中に、小さな女の子が登場する。この子は、軍事パレードを初めて見て、行進している人が何なのか分からない。彼女は兵士が何か知らなかったのだ。そして教えられる。
「戦争のための人たちさ。戦って、お互いにできるだけ多くを殺そうとするんだ」と。
それを聞いて彼女はしばらく考える。そして、この少女から出てきた言葉に人類の未来がかかっているようにさえ思える。
付け足しておくと、この詩のタイトルは、「The People Speak」で、『The People, Yes』という詩集に入っている。これが出版されたのは、1936年。示唆的ではないだろうか。
[原文情報]
タイトル:If It’s To Be War With Iran, Let It Be The War That Nobody Comes To
著者:Caitlin Johnstone
配信日:JUN 16, 2025
著作権:こちらをご覧ください。
原文の朗読:こちらで 聴けます。

すみません、ここから先は、Caitlin's Newsletter 日本語版のメンバー専用エリアになってます。メンバーの方はログインすると読むことができます。
まだメンバーでない方は、こちらの案内をご覧ください。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
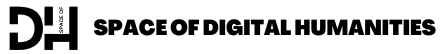

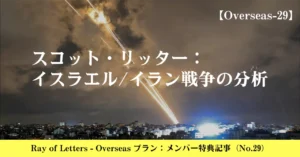
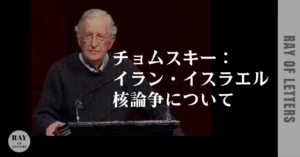



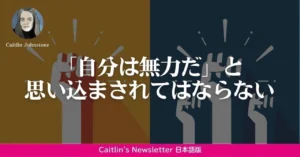

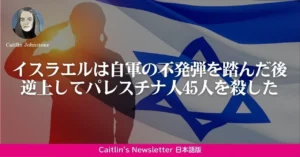


Comments