男の人に貰われやすいように、小さい頃からおつむを纏足して、内気に育てて、大きな考えを持てないように巻いてしまうのよ。足じゃないわ、頭をよ。そうして、大きくなっても、小さな動物のように可愛らしく振舞い、そんな振舞いによって男の人に愛されるように。
葉山博子『時の睡蓮を摘みに』
目次
- 日中戦争
- 女性の頭は纏足されている
- 植民地・オリエンタリズム・東亜新秩序
はじめに
かなり重症の活字中毒だった若い頃は、隙間があれば、ほとんどの時間を僕は小説の中で過ごしていた。その中から見る現実の生活は自分にとって忌まわしい雑音でしかなかった。言うまでもなく、小説を読むことが現実の逃避になっていたのだが、その一方で、それが自分の世界の旅だったことを、何十年も経って理解し始めた。
しかし、そんな霞を食うような生活はやがて終わる。雑音の奴隷になり、生活という呪縛の中でかろうじて息継ぎをしながら生きていく。ところが、それも永久に続くわけではなかった。ほんの半世紀もすれば奴隷は解放される。僕の試合も終了した。
そして、中断していた旅を始める。しかし、まわりを見回してもかつてどこにでもいた活字中毒者がもういない。生活という怨念に取り憑かれて、逃げ出せず、息絶えてしまったのだろうか。
とはいうものの、自分もあまり変わらないのかもしれない。かつて、本を開いて1ページ目の一行目からあちら側の世界に入り込めたはずが、今はしばしば余計な知識や雑念がそれに抵抗しようとする。歳を取るということは、つまらないガラクタを背負い込むことでもあるのだ。
我々はみんなそうやって、小説の世界にただひたすら無防備に揺蕩う喜びを剥奪されたまま人生の最後を迎えるのだとしたら、貴重な短い時間があまりにもったいない。
僕が言っている本の旅というのは、たくさんいろんなこと知る、雑学物知り博士になるということではない。何かを思う、何かを感じる、何かを考える、ということを経験すること。自分の頭の中の何かが起動するということ。それは間違いなく心の旅なのだが、本に引き起こされた場合、僕はそれを本の旅と呼んでいる。
葉山博子の『時の睡蓮を摘みに』で、久しぶりに、本当に久しぶりに本の旅を味わった。
いつも複数の本を並行して読んでいるので、『時の睡蓮を摘みに』も1年くらいに渡って少しずつ読み進んだ。ずーっと続けばいいと思いながら、残りのページが減っていくのを惜しみながら、少しでも寿命を引き伸ばそうとするかのように。それでも『時の睡蓮を摘みに』の中の旅の世界と、その外の日常生活との二重生活を送る日々はたった1年くらいで終わってしまった。
最後のページに至った時は、なんとも言い難い寂しい気持ちに沈んだ。もっと続けて欲しいと切に思ったが、物語はそこで終わり、僕の旅もそこで終わってしまった。また、別の旅を探すのも楽しいのだが。
日中戦争
『時の睡蓮を摘みに』の舞台は、戦前の1936年(昭和11年)に始まる。僕にとっては、母が生まれた翌年として、この物語は登録される。一般的には、日本人にとっては、二・二六事件のあった年と言えば、何か思い浮かぶことがあるかもしれない。
ヨーロッパでは、1934年8月2日、ドイツ大統領のヒンデンブルクが死去し、ヒトラーは直ちに大統領と首相の職を兼務し「国家や法の上に立ち、その意思が最高法規」であるFührer(指導者)になった。日本では、それを総統と呼び始めた。
*読んで良かったなと思ったら、投げ銭もお願いします
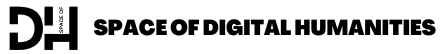


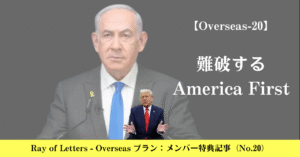

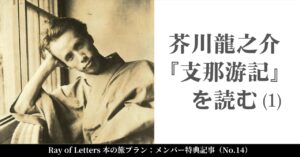
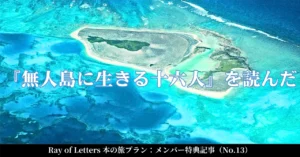
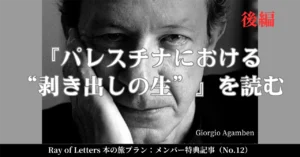
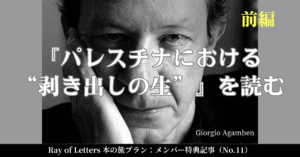
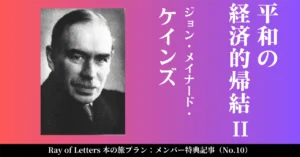
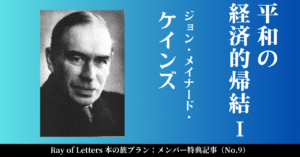
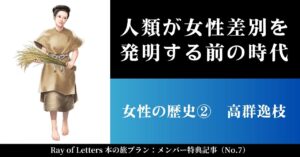

Comments