これは、Ray of Letters メンバーシップのメンバー限定記事です。詳しくは下記ボタンをクリックして、案内をご覧ください。
前々回の記事、【Overseas】国際刑事裁判所 vs ネタニヤフ 第一部
ワシントン・ポスト紙の手口で、以下のように書きました。
◾️2024年3月25日:アメリカ、国連安保理の停戦提案に拒否権を行使せず、最終的に棄権。
ここで非常に大きな問題が発生した。それは、アメリカは自らが棄権して成立した、この決議案に「拘束力はない(no-binding)」と表明し、イスラエルへの武器供給を続けているということだ。これは完全に国連システムのルールを破壊している。つまり、国際法違反ということだ。
アルジャジーラはこの問題を指摘していましたが、日本ではどう報道されたのでしょうか?いつものテレビ識者たちが熱く議論したのか、どうせアメリカが国際法を無視するのはいつものことだからと、ニュースにもならなかったのか。そうだとすれば、恐ろしいことです。
さて、前回の記事では、記事の主題から脱線し過ぎないように、以下のように簡単に説明しました。
常任理事国の棄権は、もちろん拒否権の発動と同じではない。従って、常任理事国が棄権しても、15カ国の理事国中、9カ国が賛成すれば、決議は成立する。これは、五つの常任理事国中1カ国でも拒否権を発動すれば、他の14カ国が賛成しても決議が成立しないのと対照的だ。つまり、アメリカが棄権しても9カ国以上の賛成で成立した決議は、他の全ての決議と変わらない効果を持つ。
この問題を忘れるといけないので、国際刑事裁判所 vs ネタニヤフの第二部と第三部を配信する前に、今回は先にこのトピックを取り上げることにしました。
まず下の動画をご覧ください。このガザの停戦を要求する4回目の決議案が可決された国連安保理第9586回会合に関する動画に日本語字幕をつけたものです。
この場面を最初見た時、一人でわりと衝撃を受けていました。その理由の一つは、やっとガザ停戦を要求する安保理決議が採択されたのに、棄権して成立を許したアメリカがこの安保理決議には拘束力がないと言い出したことに対してです。もう一つはアメリカの国連大使である、Linda Thomas-Greenfieldさんに関してです。彼女が今アメリカの国連大使であるのは任命された時から知っていました。
アフガニスタンが世界から絶望的に見捨てられていた頃、1998年から2000年、僕はイスラマバードを基地にする国連アフガニスタン人道調整官事務所というところに勤務していました。そこから、毎週のように国境を越えて、内戦の続くアフガニスタンに人道援助プログラムを実施するために”通う”のです。クロスボーダー・オぺレーションと呼ばれていました。当時は9.11の同時多発テロよりもずっと前で、世界中の誰もアフガニスタンのことは見ていませんでした。
Thomas-Greenfieldさんに出会ったのは、そんな頃です。彼女は在イスラマバードのアメリカ大使館に勤務する若い外交官の一人でした。国連での仕事は(職種にもよりますが)、加盟国の外交官と毎日のように会って様々な議論をします。特にフィールド・オフィスでは、同じ目的に向かって一緒に仕事する同志のような感覚が生まれてきます。何一つ真っ直ぐにうまく進むことのない環境で、希望と絶望の繰り返しの中で神経を切り裂かれながら生きている者どうしの間にだけ生まれてくる精神的・情緒的紐帯のようなものがありました。
国連機関と大使館の代表たちが集まる会議が毎週、国連人道調整官事務所で開かれていましたが、アメリカ大使館から毎回出席していたのがLinda Thomas-Greenfieldさんでした。たくさんの人に会うので、ほとんどの人は忘れてしまいましたが、数人の外交官は印象深く覚えています。そのうちの一人がThomas-Greenfieldさんです。
まず、理由の一つは、彼女が正確な難民法の知識を持っていること、人道援助の方法論についても詳しく知っていることに、ある時話をしていて気がついたことです。この人は勉強しているなと思いました。あるいは、アメリカ国務省に、そのようなトレーニング・プログラムがあるのかもしれません。妙な話に聞こえるかもしれませんが、キャリア外交官というのは、様々な分野を浅く広く知っていても、難民法や人道援助など、かなり特殊で狭い領域の専門的な知識を持っている人というのはあまりいないのです。
もう一つ印象に残った理由があります。人道援助の現場というのは、様々なジレンマの集積場所で、同じ目的に向かって仕事している人たちの間で、しばしば感情がもつれあい、怒鳴り合いになることもあります。詳細は忘れてしまったのですが、そんな何かの問題でのE mailのやりとりで、Thomas-Greenfieldさんがとても真摯な人だと感じたことがあったのです。国連にしろ、加盟国にしろ、そこに所属している人は、組織の利益と方向性/mandate の範囲でしか仕事はできません。その限られた範囲の中で、どれだけ共通の利益を追求できるかは個人の腕次第という側面もあります。30年近く前のことなのに、まだThomas-Greenfieldさんの名前を覚えていたということは、よっぽど強い印象を持ったのだと思います。
上の動画の0:27-0:31 辺りで、そのThomas-Greenfieldさんが背もたれに体重をあずけて、何かを諦観したかのように座っているのを見た時、それを見ている自分の周りの空気が固まった。諦観には「諦めること」と「悟る」ことの二つの意味があります。彼女は今、何を思っているのだろう?聡明な彼女はこのアメリカのポジションが何を意味するか完璧に理解しているはずだ。さらに多くの人が殺されるということを。
長い官僚生活で彼女はどう変わったのだろうか。今も全ての矛盾を飲み込み、その痛みに耐えながら仕事をしているのだろうか。彼女に怒りがわくわけでもない。責める気持ちにもならない。ただ、長い官僚生活のひどく重い空気が蘇ってくるのを感じていました。
*
表決(voting)に棄権はしたが、この国連安保理決議2728号に法的拘束力はないというアメリカの立場と、全ての国連安保理決議は国際法である、従って同程度の拘束力があるという国連の立場は両立するのでしょうか?
話がこんがらがらないように、問題を二つに分解します。
- 常任理事国が棄権しても安保理決議は採択され得るのか。
- 採択された国連安保理の決議に、法的拘束力はあるのか。
目 次
- 国連安保理の基礎知識
- 国連の6つの主要機関
- 国連安保理の構成
- 国連安保理の表決
- 拒否権の拒否
- 国連総会の緊急特別会合(平和のための結集)
- 緊急特別会合の法的根拠
- 緊急特別会合の関連条項
- 緊急特別会合の招集手続き
- 緊急特別会合の運用例
- 常任理事国の棄権もしくは欠席
- 棄権/欠席の効果
- 棄権/欠席の過去事例
- 結論
- 国連安保理決議の法的拘束力
- 国連憲章第25条
- Decisions という言葉尻
- 国際司法裁判所の見解
- 国連憲章第7章派
【付録】国連憲章 第5章 安全保障理事会
I. 国連安全保障理事会の基本情報
まず、0節では、国連安全保障理事会の基本的なことについて説明しておきます。分かっているという人はここは飛ばしてください。
安保理は国連の6つの主要機関(Principal Organs)の一つです。6つの主要機関は以下の通りです。
1. 国連の6つの主要機関
1. 総会 (General Assembly)
・全国連加盟国が参加する主要な討議機関。
・各加盟国に1票の投票権がある。
・重要な国際問題を議論し、勧告を行う。
・国連憲章第4章で規定。
2. 安全保障理事会 (Security Council)
・国際平和と安全の維持を担当。
・5つの常任理事国と10の非常任理事国で構成される。
・国連憲章第5章で規定。
3. 経済社会理事会 (Economic and Social Council, ECOSOC)
・経済、社会、人権、環境などの国際問題を扱う。
・専門機関や非政府組織(NGO)と連携して活動する。
・国連憲章第10章で規定。
4. 信託統治理事会 (Trusteeship Council)
・信託統治地域の管理と監督を担当。
・1994年のパラオ独立後、信託統治地域がなくなり、現在は休止状態。
・国連憲章第13章で規定。
5. 国際司法裁判所 (International Court of Justice, ICJ)
・国家間の法的紛争を解決する国連の司法機関。
・ハーグに拠点を置き、国際法に基づいて裁定する。
・国連憲章第14章で規定。
6. 事務局 (Secretariat)
・国連の行政機関で、事務総長が率いる。
・国連の全体的な業務運営を支援し、各機関の調整を行う。
・国連憲章第15章で規定。
2. 国連安保理の構成
次に安保理の構成についてです。
◾️5カ国の常任理事国(Permanent members)と10か国の非常任理事国(Non-permanent members)の合計15カ国から構成される。
◾️常任理事国も非常任理事国も一国一票の投票権を持つ。
常任理事国(P5):
◾️常任理事国の任期は無期限。
◾️常任理事国は、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの5カ国でこのメンバーは変わることはない。
◾️常任理事国は拒否権を持つ。
◾️常任理事国はPermanent のP をとって、P5と呼ばれる。
非常任理事国(E10):
◾️非常任理事国の任期は、任期2年。
◾️地域バランスを考慮して総会で投票によって選出される。
◻︎地域ごとの割り当て数は以下の通り。
・アフリカから3カ国
・アジア太平洋から2カ国
・東ヨーロッパから1カ国
・ラテンアメリカ・カリブ海から2カ国
・西ヨーロッパその他から1カ国
◾️非常任理事国に拒否権はない。
◾️非常任理事国は総会の選挙で選ばれるので、Elected のEをとって、E10と呼ばれる。
3. 国連安保理の表決
安保理での投票(voting)は、日本語では「表決」と訳されます。この表決に関しては、単純多数決ではなく、一部理事国にのみ拒否権があるという、かなり特殊な様式が国連憲章に規定されています。
◾️採決の条件:
・全15理事国のうち9か国以上の賛成が必要。
・常任理事国がいずれも拒否権を行使しない場合。
◾️拒否権:
・常任理事国が拒否権を行使すると、他の14か国が賛成しても決議は否決される。
4. 拒否権の拒否
一般にはあまり認知されていないようですが、全ての議題において、拒否権を使えるわけではありません。以下で説明するように、拒否権が適用されないケースもあります。
◾️拒否権が適用されないケース:
◾️手続事項に関する議決
国連憲章第27条第2項に基づき、手続事項に関する決定には常任理事国の拒否権は適用されない。手続事項の決定は、15理事国中9か国の賛成があれば成立する。
例: 議題の採択や議事運営に関する事項。
◾️総会に対する報告の採択
安保理が国連総会に報告する際の内容決定は、手続事項と見なされるため、拒否権の行使はできない。
◾️手続事項か実質事項かの判断が議論となる場合もあり、場合によっては常任理事国がそれを争うことがある。
拒否権が適用されなかったケースとしてよく知られているのは、ハンガリー動乱時の安保理決議です。
◾️拒否権が拒否された例:
国連安保理決議120号(1956年)
これは、ハンガリー動乱におけるソ連の軍事介入に関して、国連総会の緊急特別会合(emergency special sessions)、いわゆる平和のための結集決議を招集することを目的としており、当然ソ連は安保理で反対票を投じたが、緊急特別会合を招集するという議題は「手続事項」に該当したため、拒否権が適用されなかった。つまり、ソ連の反対票は決議の採択を阻止することはできなかった。投票結果は、賛成: 10票、反対: 1票(ソ連)、棄権: 0票だった。
5. 国連総会の緊急特別会合(平和のための結集)
上で緊急特別会合(Emergency Special Sessions = ESS)という言葉が出てきましたが、これはこの記事の主題である安保理の機能ではなく、総会の機能ですが、関連するのでここで説明します。
緊急特別会合は、国連安保理が拒否権の行使や政治的対立により行き詰まり、機能不全に陥った際に、国連総会が平和と安全の維持に関する行動を検討するための特別会合です。議題が国際社会の平和と安全の維持に関することなので、「平和のための結集」会合(Uniting for Peace)とも呼ばれます。ただし、総会の決議なので拘束力はない。
国連憲章そのものには、緊急特別会合に関する直接の規定はありません。しかし、緊急特別会合は国連総会議事規則の「平和のための結集」決議(Uniting for Peace Resolution, 決議377A(V))に基づいて開催することが出来ます。この決議は1950年に採択され、特定の状況下で緊急特別会合を招集する権限を明確にしました。
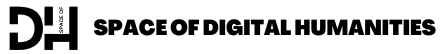




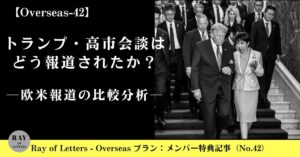
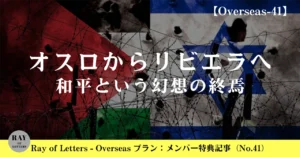
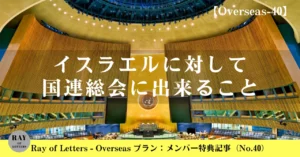


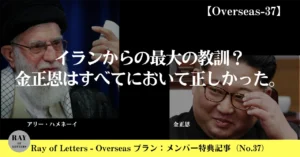
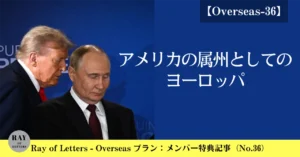
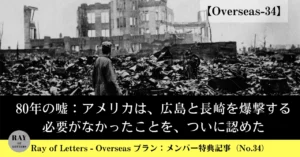
Comments