麺屋の鬼ばばあ
数日前、妙に嬉しいことがあった。心躍る体験というか。
ホテルから街の中心部へ続く道の歩道を歩いている時、ふとその道の反対側のこっちと対面する歩道でベトナム特有の低い椅子に座ってくつろいでる女性がこっちを見て手を振ってる。え?え?え?とクエスチョンマークが三連発くらい出たと思う。それに続いて、そんなバカなという思いがわいてきたのだけど、ここは即座に手を振り返さなくてはいけないと思い、僕も思いっきり手を振った。
この女性は、僕がほぼ毎朝行く麺屋さんを仕切っている女性で、推定年齢は84歳くらいだと思う。最初は中々入りにくかった。この女性の表情がものすごく怖かったのだ。誰であっても近寄った者はすごい形相で睨む。死んでも笑顔を見せないという決意がほとばしってる。ドラム缶と同じくらいの直径の深く巨大な鍋を三つドラムセットのように路上に出して、リンゴ・スターのポジションで注文をさばいてる。
言葉が分からないので、鍋の一つを指さして、「これ」というと、地獄の底から振り絞ったような低い声で「おお」みたいな返事が返ってくる。
この店にはもう一人、若いめの女性がこまねずみのように働いていて、彼女が鬼ばばあ(と僕が心の中で勝手に呼んでる)に絶対服従してる空気がまたすごい。鬼ばばあの指令一つで文字通り走り回る。これは、嫁と姑の関係かなあと勝手に思っている。
この嫁(と勝手に呼んでおく)の方も笑顔を見せない。必死で隠してるような笑顔の無さからすると、鬼ばばあからそういう指令が出ているのかもしれない。
1週間くらい通ったがいっこうに我々の関係に改善の兆しが見えなかった。それがある日、鬼ばばあがいつも同じものを食べてる僕に別の鍋を指して、何か言っている。「おお、おお」という低い唸り声しか聞こえないのだが、これを食べろと勧めてるらしいことは分かる。僕は「イエス」と言ったが、もちろん通じないので、首を思いっきり縦にふり、肯定の意思表示をした。
それは、でんごい骨付き肉の塊りが入ってとても美味しいものだった(上の写真)。食べ終わって、お礼を言いたかったが、余計なことを言ったら、地獄の業火で焼かれるかもしれない。しかし、ここで関係改善の一歩を踏み出さないといつ踏み出す?と思って、帰り際に鬼ばばあに向かって「美味しかったよ、It was so good !」と言って、アメリカ人が大袈裟にするように、両手でサムズアップをした。鬼ばばあは「おお」とドスの効いた声で答えてくれたが、もちろん笑顔はなかった。

屋根裏部屋の鬼ばばあ
麺屋の鬼ばばあに恐怖感はあったが、嫌悪感は最初から一度も持たなかった。
僕には、”おばあちゃん”という存在がなかった。父方の祖母も母方の祖母も僕が生まれた頃には、もうこの世にいなかったからだ。小学生になる頃より前だったと思うが、父母が「おばあちゃんが生きてたらなあ、喜んだやろなあ」とよく話していたのを覚えている。自分たちの子ども、つまり僕と妹を見せたかったということらしい。どうして、それがおばあちゃんを喜ばすのかは、その頃は全然分からなかった。
その頃、つまり幼稚園児の頃、僕は初めて鬼ばばあに出会った。ある時、母は僕をお絵描きという習い事に通わせることにした。絵を描くのが好きという意識はなかったと思うが、絵を描きたいという欲求があったのは覚えている。母の口紅で家の階段の一段ずつにデザインを描いていって、火のように怒られたのを覚えている。
幼稚園児の頃、映画を見に行くというのは、家族の一大イベントだったが、映画館に行くたびに映画館の外壁に描いてある巨大な絵に僕は魅入っていた。あんな大きな絵を描きたいという欲求があったのをはっきり覚えている。当時は、電子仕掛けのパネルとかCGで描かれた絵とかあるわけがなく、本当に絵描きが映画館の巨大な絵を描いていた。
そんな子どもを見て、これは良いと母は僕をお絵描きに通わせたのだろう。デイケア・センターなどない時代なので、忙しい父と母は子どもをなんとかしないといけない。そこに登場したのがお絵描きに通わすというアイデアであったのだろうと思う。
お絵描きを教えてくれる場所は、江戸の時代劇に出てくるような油屋の屋根裏部屋だった。その頃、僕が住んでいた街には古い街並みがまだ残っていた。江戸時代初期から続く日本酒の醸造所が現役で稼働していた。油屋の屋根裏部屋はいつも薄暗く、槍や鎧や足軽のかぶる笠のようなものが無造作に置いてあった。そこに鬼ばばあがいた。白髪と黒髪が混じり、長い毛を雑にまとめていたと思う。洋服ではなく、暗い色のもんぺとちゃんちゃんこのようなものを着ていた。ものすごく怖い顔で鬼ばばあは何があってもニコリともしない。幼稚園児の僕にはお化けとしか思えなかった。しかし、子どもがはしゃいでいても、怒ることはなかった。子どもが描く絵の手直しをしてくれるのだが、落書きでしかない子どもの絵が見違えるように改善して本当の絵画になってしまう。僕は感嘆して鬼ばばあを尊敬した。
初日で鬼ばばあが怖くないどころか、凄い人なのだと分かり、それから僕は一人でその屋根裏部屋にお絵描きの道具箱を持って通うようになった。母の作戦は成功した。
鬼ばばあは怖い人じゃないし、悪い人じゃないという刷り込みがその時に出来たのだと思う。だから、麺屋を仕切る鬼ばばあに出会った時も、恐ろしさに腰が引いたが、それは嫌悪とはまったく違った。
サムズ・アップ
だいぶ話がそれてしまった。
鬼ばばあの麺屋は朝6時くらいに開いて、出勤前の人でいつも賑わってる。午前9時頃には閉めて、午後5時くらいにまた開く。日中は暑過ぎて、人通りが少ない。みんな家の中に籠るそうだ。僕はその麺屋ではいつも朝しか食べたことがなかったのだが、夕方は何を出すのか興味があって一度行ってみた。
やはりすごく賑わっていて、急ぐ用事もないので、しばらく路上に立って見学していた。鬼ばばあはドラムセットをフル回転で叩いているように見えた。すべての鍋の中の内容が変わってる!わー、なんやろ、どれか食べたいなあと思うが、何がなんだか分からない。すると、鬼ばばあはこっちをジロッと見て、鍋の一つを指して「おお、おお」と言ってる。僕は「うん、うん」と言って、座る椅子が空くのを待っていた。
そのどんぶりには小さな厚揚げと袋茸がいっぱい入っていた。どちらも大好物なので、大満足だった。食べ終わって、お礼を言いたいので、また「美味しかった、It’s so delicious!」と言って、精一杯笑顔を作って、両手でサムズアップをしたが、やはり鬼ばばあは何も言わず、顔の表情もピクリとも動かなかった。

が、今回は、なんと鬼ばばあが、僕と同じようにサムズアップの形を自分の指で作ってこっちに向けている!
何も言わない。ニコリともしない。しかし、胸がときめいた。コミュニケーションがあったと感じた。これはこの麺屋に通って2ヶ月目くらいのことだった。それからも、朝の麺屋に通ったが、鬼ばばあはやはりいつもと同じで笑顔というものは決して見せなかった。彼女の歴史に何があったかまったく知らないが、悲しみや、怒りや、辛さや、諦めや、不信や、忍耐や、警戒の長い歴史があの極端に無表情な顔に積み重なっているように感じた。
日本の昔話には、山姥(やまうば)という恐ろしい形相をした老女という型が様々なストーリーとなって登場する。西洋の昔話にも森に住む恐ろしいおばあさんや魔女がいる。もちろん、どれも人間の想像力がふんだんに使われた作り話であるだろうが、まったくの無から出てきたものとは思えない。その元になる現実があったのだと思う。山姥は女性の不遇という長い歴史の産物ではないか。こき使われ、虐げられ、やがて歳をとって老婆になり、山に捨てられる。姥捨山はもうないにしても、女性の境遇は実際のところあまり変わってないのではないかと思う。

麺屋の鬼ばばあにしろ、お絵描き屋根裏の鬼ばばあにしろ、寡黙で表情を失ったあの険しく恐ろしい顔の裏には女性の歴史が詰まっているように思えてしょうがない。しかし、お絵描きに通う子どもの心には、鬼ばばあの恐ろしい形相は簡単に溶けてなくなり、「この人はいい人」カテゴリーに入ったのだろう。ずっと意識の外にあったその記憶が、麺屋の鬼ばばあにも通じたのかもしれない。
冒頭に書いた心躍る体験をしたのは、この麺屋に通って3ヶ月経った頃の話だ。それにしても驚いた。道路の向こうから鬼ばばあが手を振っている。しかも、笑顔だったのだ。
* * *
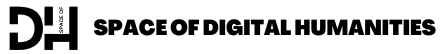











Comments
List of comments (8)
良いお話で、胸がじーんとしました。人間同士、言葉や表情の奥にあるもので通じ合うの、いいですね。
伝わってると感じた時の、何とも言えない喜びは本当に大きかったです。
この笑顔は嬉しいですよね。
鬼ババアを笑顔にさせたヨシさんは凄いですw
私も鬼ババアに成長しないように笑顔を忘れないように過ごそうと思いました。
世間に笑顔を振りまいてください。
寄り付き難い麺屋のお婆が、通じ合う何かを感じ常連客と見なして感情を緩める3か月...変わらぬ付き合い方が互いの安心感と信用を作るんだなぁ。
お互いに認知できるようになってからも、
婆さんの馴れ合わない態度がとても心地よいです。
拝読していると、映像を真ん前で観ているような気もしまして、自分の空想具合にもビックリしながら、お話に感動しました。
実は私、ゲラ子なので声出して笑ったり。
人情噺でもあり、幾重にも面白い!
国内外の民話ファンとしては山姥や鬼というワードに、また深い意味を感じたり。
もしかすると地元の常連さんは笑わない事の事情がわかっている人も中にはいらっしゃるかもですが、言葉が通じなくても事情を知らなくても真心は感じ合えたり。
終わりのお婆さんの笑顔の手振りシーンが最高に素敵!
読んで頂きありがとうございました。
僕も何かを読む時も書く時も頭の中で映像化する癖があります。
言葉はそこにたくさんある成分の一つと思ってます。